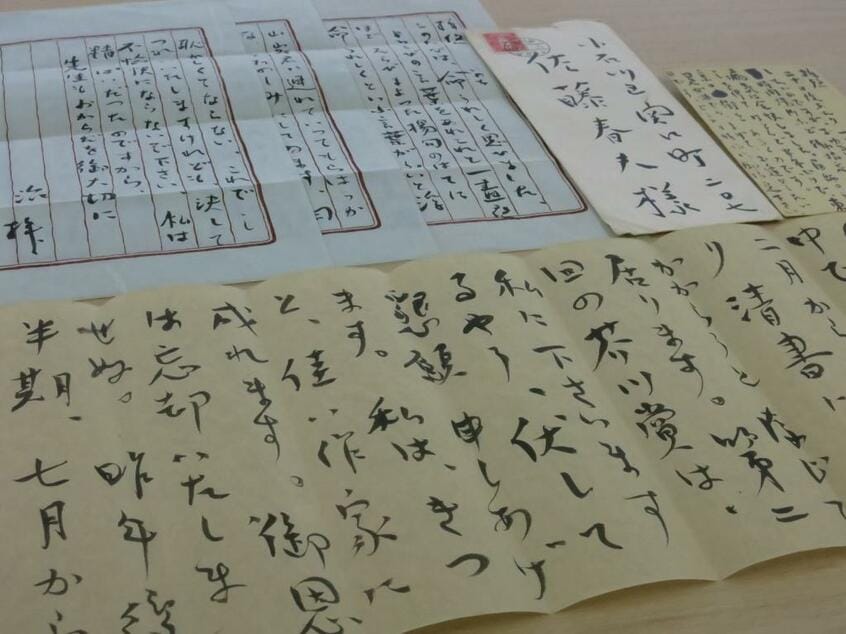
「実に大なる田舎者である」「創造力というものが無いんだね」「そんなキタナイ小説は嫌いだ」「馬鹿!」「オタンチン、パレオロガス」――。夏目漱石、尾崎紅葉、正岡子規、田山花袋、石川啄木など、明治・大正・昭和に活躍した文豪たちの「皮肉」「嘆き」「怒り」の言葉を集めて紹介した『文豪の悪態』(朝日新聞出版)。本書の著者で大東文化大学教授の山口謠司氏が、個性にあふれ味わい深い、文豪たちの語彙の一端を紹介する。
* * *
文豪とは、すなわち文学や文章で際立つ力を持った人のことをいう。すぐに思い浮かべるのは、森鴎外、夏目漱石、永井荷風、川端康成、太宰治などであろう。
しかし、文豪の生活を見ていると、何とも不思議というか、常識では考えられないような「悪態」をついて「目立つ」人たちが少なからずいることに驚かされる。そして、相手を罵ったり、悪口を言ったりするのにも、やはり、文豪ならではの表現をしているのだ。
いくつかエピソードを紹介しよう。
中原中也は、昭和8(1933)年の晩秋のある寒い夜、坂口安吾、太宰治と酒を飲んだ。
そして、酔いが回ると、太宰に向かって「何だ、おめえは。青鯖が空に浮かんだような顔をしやがって。全体、おめえは何の花が好きなんだい?」と絡んだのだ。
「青鯖が空に浮かんだような顔」とは、「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」(『山羊の歌』所収「サーカス」)など独特の視覚と音感を持った中也ならではの表現であろう。しかし、この言葉の裏には、二歳年下の太宰のことを「青臭い」という意味がほのめかされている。
昭和8年と言えば、太宰はまだ同人誌『青い花』に「ロマネスク」を発表したばかりの無名の作家にすぎなかった。
ふたりはこの後、ぐでんぐでんに酔っ払って取っ組み合いの喧嘩をするのだが、太宰は中也に対して「蛞蝓(なめくじ)みたいにてらてらした奴で、とてもつきあえた代物ではない」と言うのである。
この太宰の中也に対する表現も、人を観察することに優れた太宰の文豪としての言葉であろう。





































