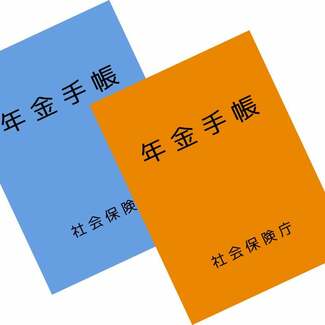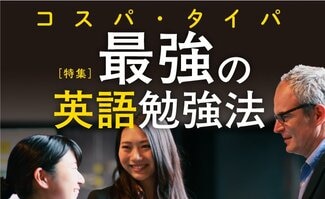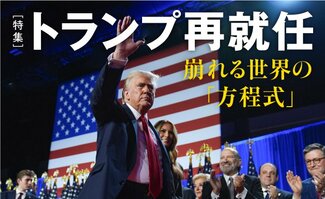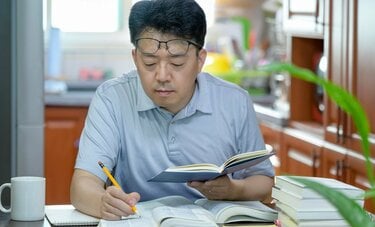また、食事の面でも、工夫をしている。独自に開発した「モアディッシュ」は、のみ込む力が衰えた人でも舌で押しつぶせてのみ込みやすくしたソフト食で、見た目も通常食のようだ。
「『流動食などをそのまま盛ると、見た目も味も、何を食べているのかわからない。何とかならないか』というスタッフの一言で生まれました」(松下さん)
隣接する協力医療機関のメディカルクリニック医庵が週に1回、ホームで診療を行う。週に1回、居室の床・水回りの清掃や買い物代行サービスもある。ホームと最寄り駅までシャトルバスを運行し、トレーニングルームや理美容室、竹林の緑を見ながら入浴できる大浴場も完備している。
一般的に、地価の高い都市部のホームほど入居金は高くなる。また、元気なうちに入るタイプのホームは居室も広く、映画鑑賞室やプールなどの豪華設備を売りにするので、高額になりやすい。
ただ、高齢者住宅情報センターのセンター長、米沢なな子さんは言う。
「元気なシニアは、外出する時間も長い。ホーム内にバーやプールの設備があっても、利用しない人もいる。それよりも大切なのは、費用に合った手厚い介護態勢と医療連携が取れているか。認知症が進んだときでも専門性の高い対応が可能か、病院から退院した後でも医療態勢がないからと退去を迫られないか、看とりの態勢は取れているのかを、きちんと見極める必要があります」
介護が必要になると不要な設備もある。先々に必要な設備も検討したうえで、予算に合ったホームを選んでほしい。
◆介護は民間の時代へ、問われる自己責任◆
多種多様な高齢者ホームが続出している背景には、増大する医療費や介護費を減らそうと、国が介護サービスを民間に開放している流れがある。これまで国頼みでよかった私たちの老後は、今や乱立する施設のどれを選ぶかを自己責任で判断せざるをえなくなりつつある。
介護保険が2000年にスタートし、それまで主に自治体や社会福祉法人が担っていた介護サービスが、民間事業者に開放された。介護サービスの供給量は一気に拡大した。同時に、有料老人ホームなどの高齢者ホームも右肩上がりで増加してきた。安い特別養護老人ホーム(特養)に入りたくても、待機者が多くて入れないためだ。