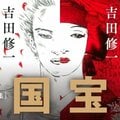「配球内容も変わった。投手の球威が上がっているから、細かい配球は必要ないのも事実。例えば、以前ならカウントを取るために裏をかいて変化球を投げることもあった。今は『真っ直ぐでファウルを打たせれば良い』というのが多い。それができるなら効率は良いし、細かいことまで考えなくて済む」
そして『打てる捕手』が評価基準になりつつある。捕手は経験により成長できるため、試合出場機会が何より必要となる。そのための近道が打つことだ。かつては65年に3冠王となった野村氏のような存在が稀だった。それが城島健司(元ソフトバンク他)、阿部慎之助(現巨人2軍監督)あたりから、強打の捕手全盛に変化した。
「極端な話、攻守に活躍しないとゴールデングラブ賞は獲れない。特に捕手はチームが勝てなくなったら最初に代えられる。『打撃でも必要』と思われないとダメ。城島や阿部も打つことで試合に出れた。そのうちに配球も覚え、完璧な捕手に近くなった。『配球で勝った』ではなく『打撃で勝った』の時代」
各球団の捕手事情を見渡すと打撃が良い捕手が多い。パ・リーグでは西武・森友哉が打線の中核を任され、バッティングでの貢献がチームの成績にも直結する。ソフトバンク・甲斐は長打も出始め勝負強く、ロッテ・田村龍弘なども同様の印象だ。
「パ・リーグ上位球団の捕手はみんな打てる。森もそうだが、甲斐も打撃力が格段に上がった。打率は低いが2桁本塁打(打率.211、11本塁打)も打っている。ロッテ・田村も同様のタイプで、大事な場面で結果を残す印象がある。『打撃で頼りになる』というイメージがつけば、相手は嫌だし監督も使う」
セ・リーグも打てる捕手全盛で、特に巨人では打撃を通じての正捕手争いが楽しみな状況。大城以外にも、シーズン後半には岸田行倫も起用された。17年ゴールデングラブ賞の小林誠司は故障も重なり、昨年はわずか10試合のみの出場と苦しんでいる。
「大城はあれだけ打つと代えられない(打率.270、9本塁打、41打点)。岸田は二軍レベルではなく(ファームで打率.313)、相手投手を見下ろす感じで打っている。一軍でもそういう風格が出て来れば面白い。小林は肩の強さは周知だが、まずは試合に出ることだ」
広島も『捕手天国」と呼べるほど。侍ジャパンでも活躍した会沢翼の打撃は球界屈指。昨年は左の好打者、坂倉将吾も起用された。勝負強い打撃の磯村嘉孝や、夏の甲子園で1大会の最多本塁打記録(6本)を樹立した、17年ドラフト1位の中村奨成もいる。