
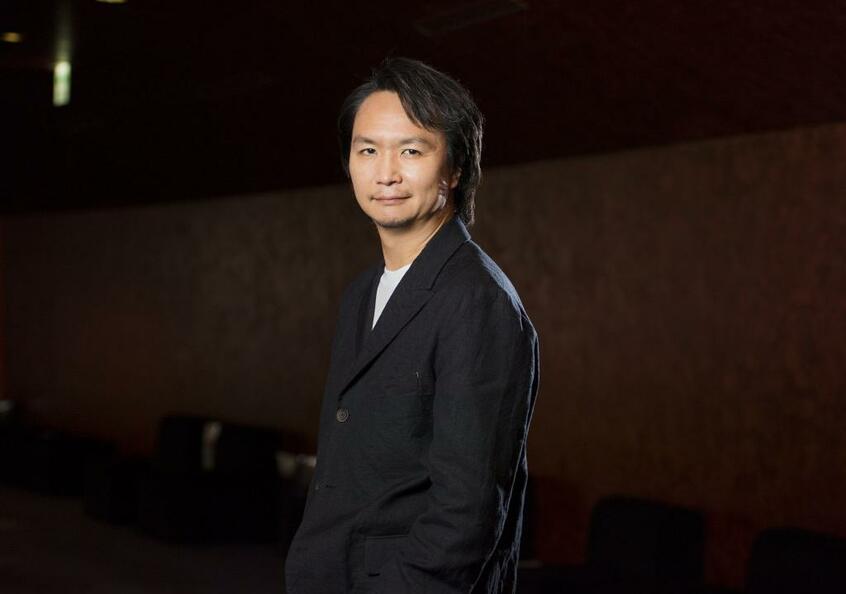
相次ぐ公演延期や中止で大きな影響を受けたエンターテイメント業界。劇作家の長塚圭史さんはコロナ禍に、どんな思いで演劇に向き合い何を感じたのか。
* * *
世の中から“不要不急”の産業だと烙印を押されてしまった──。昨年の春、緊急事態宣言が発令されたとき、多くの演劇関係者は落胆した。長塚さんも、2017年に旗揚げした演劇ユニット「新ロイヤル大衆舎」で6月に上演するはずだった芝居が延期・中止となった。
「そのときは、メンバー4人がそれぞれ20万ぐらいの借金を抱えることになって(苦笑)。『日本の演劇を明るく照らす』をキャッチフレーズに旗揚げしたユニットが、この状況をただ手をこまねいて眺めているだけではまずいだろうと、初めて動画配信を実施しました」
「緊急事態軽演劇八夜」と題した朗読劇は、シェイクスピアの「夏の夜の夢」や、チェーホフの「ワーニャ伯父さん」といった名作と呼ばれる古典のほか、日本の無声映画の脚本を掘り起こし、朗読用にまとめた。
「下北沢のザ・スズナリにお客様を35人入れて、毎晩動画配信もしながら読み語り芝居を上演しました。これがすごくいい経験で、『配信のもっともいい形は朗読じゃないか』という手応えを感じましたね。通常の舞台だと、お客様の目がカメラになって、自分の好きなように場面を切り取って、スイッチしていくことができるけれど、普通の演劇を配信にして、動いていく俳優をカメラが捉えると、どうしても芝居への参加度が下がってしまう。でも、朗読劇だと俳優は動かないし、新ロイヤル大衆舎の4人は、顔面で癒やしを与えるようなメンバーではないから(笑)、セリフとお客さんの想像力が結合することによって、舞台への参加度が上がるんです」
リモートでの稽古のとき、最初は誰もが「ここの心情はわからない」を連発していたチェーホフの戯曲が、本番では最も楽しんでできたという。
「稽古のときは、『こいつ何考えてるかわからない』『なんでこんなことを始めちゃったんだ』なんて、50前後の演劇人4人が、それぞれ愚痴や文句ばかり言っていたんですが、話していくと、だんだん道筋が見えてきた。毎日違う作品を7日間上演してクッタクタになったけど、本番は楽しかったです(笑)」





































