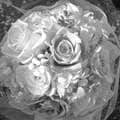「飾りじゃないのよ涙は」のシャッフルビートには、そんな戦後ポップスに通じる趣がある。思えば、明菜は母親の影響で、幼い頃に美空ひばりをよく歌っていた。陽水は彼女にこうしたサウンドが合うことも、どこかで見抜いていたのだろう。
詞に関しても、またしかり。デビュー以来、現代の個人的な孤独や不安を表現してきた陽水は、明菜のなかの「鬱積」の正体にも気づけたのかもしれない。それは、彼女が「泣きたがっている」ということだ。この作品の最大の魅力は、歌手自身がそういう衝動を心地よく解放しているところにある。
また、そこには聖子が築き上げた世界観への明菜的回答という側面も見られる。涙を真珠やダイヤにたとえたりする聖子のスタンスを、涙は真珠でもダイヤでもないといちいち否定したうえで、とかく「うそ泣き」云々といわれた涙の使い方(?)にまでツッコミを入れているかのようだ。陽水はテレビを見るのが大好きな、遊び心のある才人なので、ふたりのコントラストを面白がりながらちょっと仕掛けてみたのかもしれない。
それはさておき、聖子のラブソングはもっぱら男女の駆け引きが描かれ、いわば虚構的な面白さを優先するものだった。しかし、この作品で明菜はどこまでも真実の愛を希求しており、それが彼女自身のキャラともあいまってリアルな感動を呼び起こした。
ただ、明菜と陽水の本格的接近は、ここだけで終わる。これが聖子の場合だと、たとえば松本隆が旗振り役として集めた松任谷由実、細野晴臣、大瀧詠一らがチームを組み、強力なサポートをしていたわけだが、明菜にはそういうものはなかった。
こちらもさまざまなアーティストから作品提供をされているものの、チーム感は希薄だ。玉置浩二やタケカワユキヒデ、加藤登紀子あたりはともかく、高中正義や松岡直也のようなジャズやフュージョン畑の人もいて、多士済々ともいえるし、バラバラという印象もある。それゆえ、聖子がひとつの凝縮された世界観を築き上げたのに対し、明菜はスケールの広がりや多様性といった世界観で勝負することとなった。