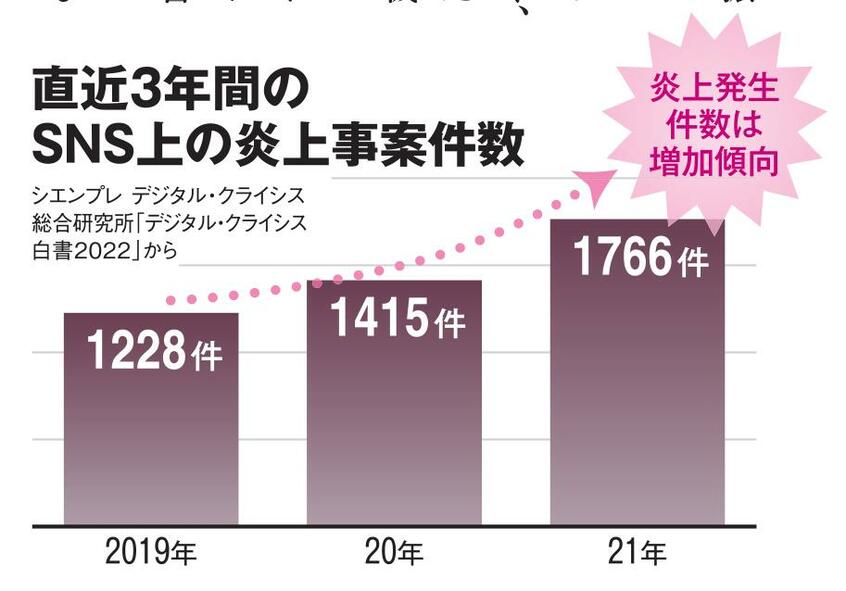
SNSに詳しいITジャーナリストの鈴木朋子さんはSNSでの炎上についてこう指摘する。
「ツイッターのようなSNSは書き手と読み手が別の社会に属していて共通認識がありません。意図と違った取られ方をすることはよくあります。また、知り合いに見られる意識がないため熱くなって乱暴な言葉を使ったり余計なことを書いたりしやすい。叩く側も批判しやすく、ひとつ間違うと簡単に炎上します」
スポーツの話題で他チームファンからの批判が集まるのは一般的な炎上のパターンだという。
先出の男性の場合は実名とはいえプライベートで使っているアカウントだったが、ビジネスツールとしてSNSを使う人も増えている。また、企業がPRのために運用するアカウントも多い。鈴木さんは続ける。
「個人でも企業でもビジネス目的でSNSを活用する機会は増えています。当たり障りのない発言は話題になりにくいのでついとがったことを言いがちですが、受けを狙った投稿が別の誰かを不快にさせてしまうケースがよく見られます。そもそも大企業や『プロフィルが充実している人』は叩かれやすく、批判が批判を呼ぶ傾向があります」
過去には大手家電メーカーの製品PRアカウントがゲームソフトの価値を独自に価格に換算、「価値0円」としたソフトもあって大炎上した例があった。その後、同アカウントは運用を停止、同じメーカーの別の公式アカウントが「だれかの好きや思い入れを否定することは決して許されません」と謝罪した。
SNSの累計フォロワー80万人を抱える精神科医で作家の樺沢紫苑さんは、SNS上での振る舞いについてこう指摘する。
「普段友達と会話する中でなら許されるような冗談や悪口でも、インターネット上では通用しません。ネガティブな発言や過激な言動は注目を集めることもありますが、炎上系ユーチューバーなどを見ていてもうまくいった試しがない。SNSに何か書くときは、1千人の目の前で同じ発言ができるのかを判断基準にするといいと思います」
(編集部・川口穣)
※AERA 2022年12月12日号より抜粋






































