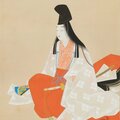沢木は、そうした書評を書いてしまったのは、世代の近い外岡に対する嫉妬心であったということをそのエッセイで正直に告白している。で、外岡にあわす顔がなかったのだが、しかし、外岡は、その書評を、「感謝している」と言ったのだった。
沢木のエッセイのきもはそれからだ。この顛末を原稿にして朝日新聞に連載していた「彼らの流儀」の一回分にしようと、外岡に原稿を送って掲載の許可を求めたところ、こう言われて断られてしまうのだ。
<自分はこれまで、かつて小説を書いたことのある外岡秀俊ではなく、朝日新聞のごく普通の記者のひとりとしての外岡秀俊であることを意志してきた>
『北帰行』の中で外岡は、社会主義者、無政府主義者としての啄木と吟遊詩人としての啄木をどう考えたらいいのか、ということを主人公の「私」に追わせている。それは常に分裂したものとして批評家からとらえられていた。しかし、と主人公である「私」は啄木の北海道時代の足跡をたどったすえに次のような結論に達するのだ。
<啄木が大逆事件に異常なまでの関心を抱いてその真相を究明したのは、彼が一人のジャーナリストであったためというばかりではないだろう。彼は詩人であったからこそ、国家の犯罪を糺明せずにはいられなかったのではないか(中略)。彼はくらしの中にできた歌の小径を通って、無政府主義に赴いたのだった>
これは、その後外岡が朝日でたどることになる道をそのまま予言していた。
沢木には、「小説家外岡」は封印している、ときっぱり言ったが、しかし、外岡の書く記事は、小説家としての自由な心から対象に迫る面白さがあった。
外岡は、いわゆる「前うち」をやってこなかった記者だった。記者クラブに属して、官僚から情報をとり、それを他社より早く書くという取材はしていない。すぐに学芸部に配属され、記者クラブも発表もない世界で、鷹匠を取材したり、クリムトとヒトラーを生んだ大戦前のオーストリアについて書いた。これらの文章は今読んでもまったく色あせていない。