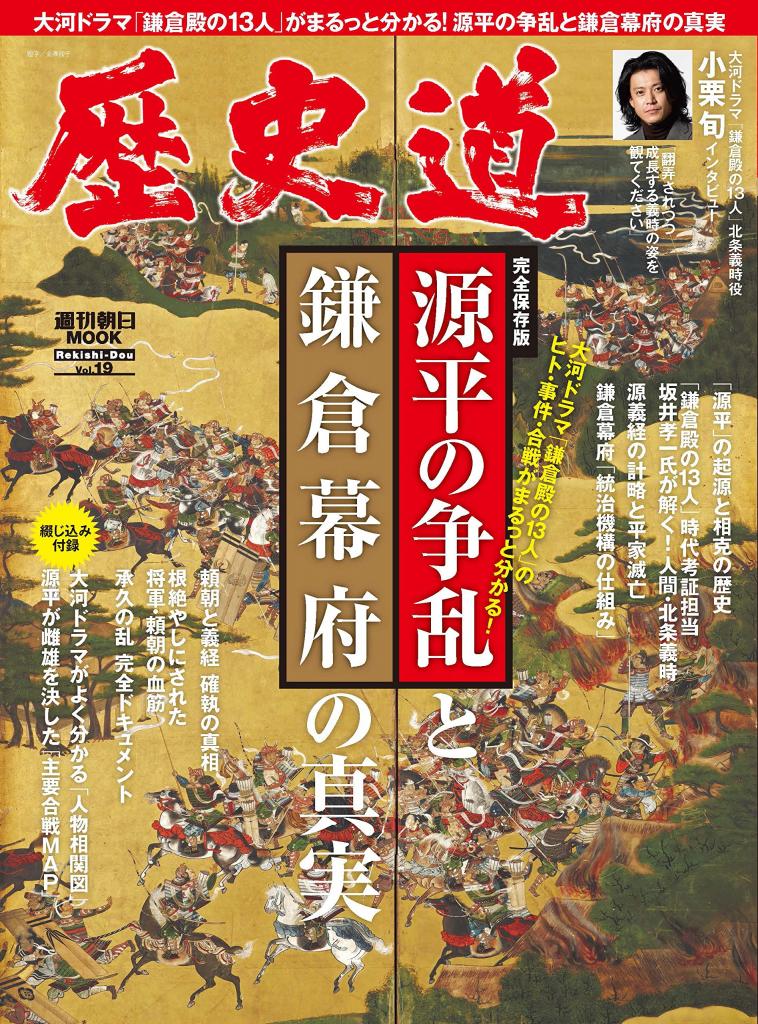
その後、正治元年(1199)正月十三日、源頼朝が死去すると、家督は長男の頼家が継承した。18歳の若き武家の棟梁の誕生である。しかし、わずか3カ月後には、訴訟を直接裁断することが禁止されてしまう。
鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡』の同年四月十二日条には次のような記述が載っている。「諸訴論のこと、羽林(頼家)、直に決断せしめ給うの条、これを停止せしむべし」と。そして同書には続いて、「今後、大小のことにおいては、北条時政、北条義時、大江広元、三善康信、中原親能、三浦義澄、八田知家、和田義盛、比企能員、安達盛長、足立遠元、梶原景時、二階堂行政らが談合し成敗せよ、その他の者が訴訟のことを執り行うことはできない」とある。
この一文が、頼家が訴訟に直接判決を下すことが停止され、有力御家人十三人の合議制に決裁が委ねられた事を示すと以前は考えられてきた。『吾妻鏡』には、傍若無人な態度をとる頼家の姿も記されているが、これも頼家の直接判決が停止された説の裏付けとされた。
ところが、今ではこうした見解は有力ではない。有力御家人十三人の合議制に決裁が委ねられたとされる『吾妻鏡』の記述は、頼家への訴訟の取次を有力御家人十三人に限定する事を定めたに過ぎないと解釈されるようになってきたのだ。しかも、十三人の宿老が一堂に会して合議した例は確認されない。もちろん、何人かが集まって相談する事はあったであろう。よって、「十三人の合議制」なるものも、実体はないものといえる。そもそも、『吾妻鏡』自体に、それ以後も、頼家が積極的に相論に関与する事例が載せられている。
陸奥国(宮城県)の新熊野社の社領の境相論に際して、頼家が「土地の広い、狭いは、その身の運・不運による。よって使者を派遣して現地を実検することは不要。今後、境相論はこのように決める。もし少しでも理を尽くしてはいないと思う者は相論をしてはならない」と言い放った事はよく知られる。これは同年五月のことではあるが、六月には、梶原景高の未亡人に所領を安堵した。




































