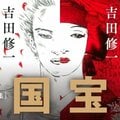東京・神保町の老舗映画館「岩波ホール」が54年の歴史に幕を下ろした。世界の映画人が厚い信頼を寄せてきた同館。その“終わり”が意味するものとは。AERA 2022年8月8日号の記事から紹介する。
* * *
いろんな国の映画を見せてくれる特別な映画館──。岩波ホールが「新型コロナの影響による急激な経営環境の変化」を理由に7月29日に閉館した。
閉館前、ずらりと並んだ過去の上映作のポスターを眺めていた女性(64)に声をかけると、初めて岩波で見た映画は、サタジット・レイ監督の「大地のうた」3部作だったと言う。
「ここに来れば面白い映画が見られた。タルコフスキーの『惑星ソラリス』、『BLACK& WHITE IN COLOR』は私にとって初めてのアフリカの映画。アンゲロプロスの『旅芸人の記録』や南果歩さんのデビュー作『伽や子のために』(「や」は、にんべんに耶)などどれも印象深いです」
今年2月に岩波ホールでジョージア映画「金の糸」を上映した映画会社ムヴィオラの代表、武井みゆきさんはジャン・ルノワール監督の「大いなる幻影」(1976年公開)が初の岩波体験だった。
「中学生だった私にはさっぱりわかりませんでしたが、親が連れていってくれた映画とは違いました。『フェリーニの道化師』は感動して大泣き。ヴィスコンティの『家族の肖像』は『大人の映画に出会ってしまった!』という感動がありました。クストリッツァ、オルミ、アンゲロプロス……。素晴らしい監督たちの映画を初めて紹介したのはみな岩波ホール。ここは世界を見せてくれる『窓』でした」
ホールは68年2月にオープン。当初は映画、音楽、古典芸能、講演会が中心の多目的ホールだった。ミニシアターの先駆けのように言われるが、95年に総支配人の高野悦子さん(2013年没)に取材した際、
「もともと小さな土地でしたからできたホールも全席で232という小さなものでした。最初から経済効率を考えて小さな劇場として造られる今のミニシアターとは基本的に違うのです」
と語っていた。
埋もれた作品を発掘
多目的ホールから映画館へ移行していったのは74年。レイ監督の「大樹のうた」の上映を機に、高野さんと映画界の重鎮で東和(現・東宝東和)の故・川喜多かしこさんが、岩波ホールを根拠地に世界の埋もれた映画を世に紹介する運動「エキプ・ド・シネマ(フランス語で、映画の仲間たちの意)」をスタート。会員組織を作り幅広い層の会員を得たことで、エキプを大きく発展させる原動力になった。
「岩波ホールは世界の埋もれた映画を上映していこうという方針上、ヒットしそうな映画はここへはきません。作品が長くて難解で知名度がないというような作品しかこないんです」
そう高野さんは笑っていたが、それこそ劇場の個性。東宝東和、フランス映画社、日本ヘラルド映画といった当時の配給会社と協働しながら、映画史に名を残す名匠の名作からアジアや中南米、アフリカなど世界中の名作を発掘。映画ファン、世界の映画人から信頼を得ていった。