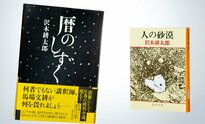1938年、玉川電気鉄道の本線に当たる玉川線が発着する渋谷駅ターミナルビル(玉電ビル)の高架改築にともない、天現寺線は玉川線と路線分断されてしまった。この結果、天現寺・目黒両線の電車運用は東京市電から電車を借りて営業を継続した。1948年2月に、東京横浜電鉄の後身である東京急行電鉄は両線を東京都に譲渡し、都電路線としての歴史が始まった。譲渡後は中目黒~築地を結ぶ都電8系統として、1967年12月の路線廃止まで走り続けた。
1906年10月30日、山手線に乗降客を扱う「恵比寿」旅客駅が開業した、恵比寿駅は原宿駅とともに私鉄であった「日本鉄道」最後の新駅として開設され、開業の翌日に国有化されている。駅開設当初の地名は「下渋谷」であったが、現在は駅に通じる道は「恵比寿通り」に、周辺の地名も渋谷区・恵比寿になっている。ブランド名を地名に転化させて、大いに発展したのが恵比寿だ。
余談であるが、サッポロビール工場の操業が廃止された時代、遊休した貨物扱施設を利用して、九州や北海道方面への「カートレイン九州」「カートレイン北海道」が多客シーズンに運転されていた。
「カートレイン」は恵比寿貨物駅で自家用車をフォークリフトで貨車に積み込み、乗客は寝台車に乗車。恵比寿駅を発車して目的地までノンストップで向かう。翌朝は小倉貨物駅(北九州)や白石臨時駅(札幌)に到着後、自家用車で目的地へ、というフレーズの利便性の高い行楽列車だった。
著者も何度か恵比寿駅から九州まで、「カートレイン九州」を利用した。「新幹線+レンタカー」「航空機+レンタカー」とは違う、味わい深い旅の体験だった。
■撮影:1964年7月4日
◯諸河 久(もろかわ・ひさし)
1947年生まれ。東京都出身。写真家。日本大学経済学部、東京写真専門学院(現・東京ビジュアルアーツ)卒業。鉄道雑誌のスタッフを経てフリーカメラマンに。「諸河 久フォト・オフィス」を主宰。公益社団法人「日本写真家協会」会員、「桜門鉄遊会」代表幹事。著書に「都電の消えた街」(大正出版)「モノクロームの東京都電」(イカロス出版)など多数。