


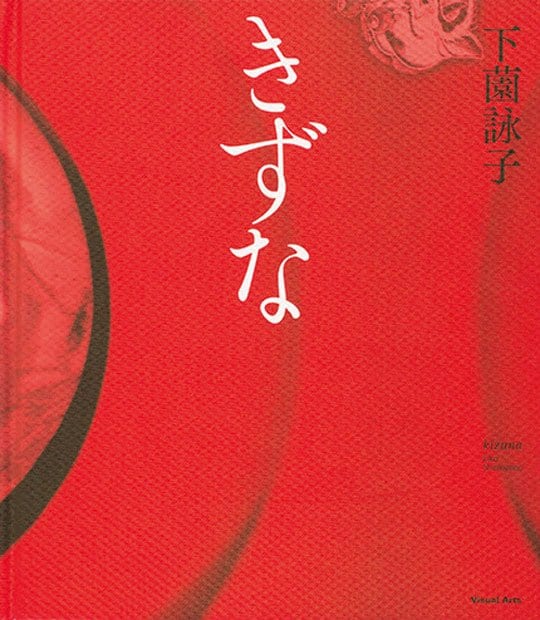



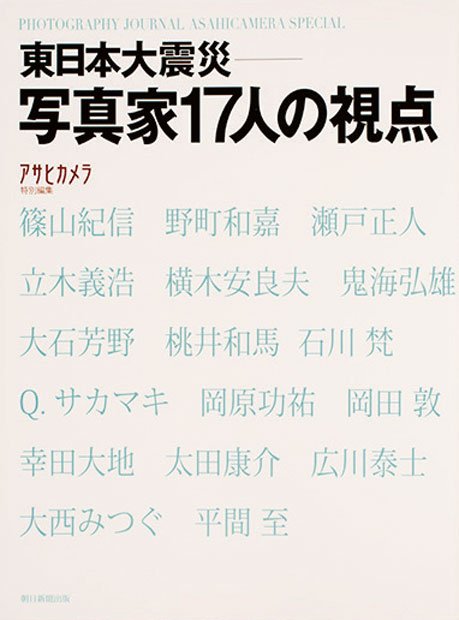



写真史と肖像権
2011(平成23)年1月号には、特集「現代写真の地図 キーワードで読み解く今昔の写真表現」が20ページにわたり掲載されている。「巨匠たちの仕事を振り返ることで、写真表現の未来が見えてくる」として、風景、ポートレート、ドキュメントについて、欧米の代表的な作家を例にとり、表現の変遷が紹介された。
ゼロ年代後半から、このような写真史についての特集が目立ちはじめている。ほかに風景、ヌード、昆虫などの各カテゴリー、または古典技法について紹介する企画も組まれた。その背景には、写真史を読み直そうという機運の高まりがあった。
ひとつの契機は、デジタル化の進展だった。有名無名を問わず、蓄積されてきた膨大な写真がウェブ上で公開されるようになり、その記録的な価値や、表現上の関連性が再発見されている。同時期の日本の写真表現への再評価も、この環境とは無縁ではない。
美術館でも写真史の研究が進み、その成果が公開されたことも大きかった。たとえば東京都写真美術館では、07年度のシリーズ展「『昭和』写真の1945-1989」から、収蔵作品によって写真史をたどり直す企画が始まり、地方でも写真史の掘り起こしが進んだ。ことに、09年の青森県立美術館での「小島一郎北を撮る」展などは、夭逝した作家の知られざる側面を浮き彫りにして高い評価を得ている。
啓発的な著作も出版された。金子隆一とアイヴァン・ヴァルタニアンの共著、09年の『日本写真集史 1956-1986』(赤々舎)は日、仏、英の3カ国で上梓され、荒木経惟や森山大道にとどまらない、日本の写真表現の多様性を示した。翌10年には、写真という文化にはその発明前史からの多様な可能性が引き継がれていると論じた、アメリカのジェフリー・バッチェンによる『写真のアルケオロジー』(青弓社)が翻訳出版。またバッチェンがキュレーションを手がけた「時の宙づり―生と死のあわいで」展もIZUPHOTOMUSEUMで開催された。
写真史それ自体を取り込んだ話題作は、10年に東京都写真美術館で開催された森村泰昌の「なにものかへのレクイエム-戦場の頂上の芸術-」展である。森村は20世紀という時代を象徴する歴史的な報道写真やポートレートに入り込んでいるが、その意図について「過去を否定し未来を作るのではなく、現在は過去をどう受け継ぎ、それを未来にどう受け渡すかという『つながり』として歴史をとらえたい」(展覧会リリースから)という、アイデンティティーを巡る問いかけだとしている。
本誌における温故知新的な特集は、こうした流れの一端にある。とはいえ、写真撮影に関する社会的環境は大きく変化しており、写真表現の継続性に困難を与えてもいた。
それが肖像権についての取り扱いで、ことに03年の個人情報保護法成立以降、スナップショットについて忌避感が生まれていた。作品発表の場を提供するギャラリーやコンテストにおいて、主催者による自主規制が目立ちはじめ、被写体の撮影許可を明確にしないかぎり、発表が認められないというケースが著しく増えていた。
典型的なケースは本誌でも起きている。それは11年4月号で発表された木村伊兵衛写真賞(以下、木村賞)の選出経緯である。この年、同賞を獲得したのは下薗詠子の「きずな」で、同世代の若い男女を正面からとらえたポートレートには、人間の傷つきやすさと再生力がみずみずしくとらえられていた。問題は、この下薗作品と最後まで競り合った蔵真墨の写真集『KURA』(蒼穹舎)だった。同作は路上で撮られたモノクロのスナップ作品で、その批評的なまなざしが評価され、最終選考に残っていた。
だが、この年から選考委員となった岩合光昭、瀬戸正人、鷹野隆大の3人は、『KURA』が肖像権の問題に抵触する可能性が高いと聞かされた。これに対して鷹野は強い疑問をいだいたものの、結局は「反対意見を突き崩すことができなかった」。そこで選評において「写真表現において重要な役割を果たしてきた路上スナップが、こうして公の場から締め出されていくことに強い危機感を覚える」と懸念を示したのだった。
揺れる写真家たち
11年は本誌の創刊85周年という記念すべき年だったが、大きな厄災に見舞われ、混乱した一年となった。いうまでもなく、3月11日に起きた東日本大震災と、その後の福島第一原子力発電所事故が招いた事態である。
震災はまず誌面づくりに直接影響を与えた。製紙工場の被災によって印刷用紙の変更やページ数の圧縮が必要となり、流通の混乱で書店への配本にも困難が生じていた。企画と営業面で痛かったのは、各カメラメーカーの工場や系列企業の被災で、多くの新製品の発表が繰り延べされたことだ。メカニズム記事や広告の目玉が消えたうえ、現行品の供給もタイトになった。ことにニコンの場合、同年10月のタイの洪水で現地工場が被災して、生産計画がさらに立ち遅れた。その反動で翌
12年は新製品ラッシュとなった。
震災について掲載された最初の記事もメーカーの動向だった。5月号のニュース欄に、被害と操業再開の情報、義援金の拠出や救助活動などがまとめて紹介されている。
写真家の震災体験が語られ始めるのは6月号から。グラビアで作品を発表した荒木は、「災害現場の映像を見ると、写真に何ができるのか。と考えてしまう」と戸惑いを率直に語っている。川内倫子は写真集『Illuminance』(フォイル)で新刊書インタビューに登場し「(震災)直後は私も無気力になったし、今だったら違う編集をしただろうかと、いろいろ自問」したが、やがて自分の方向性を再確認した。そして「こういう仕事をさせてもらっているからこそ、人の役に立ちたい。身の引き締まる思いです」と決意を表している。
9月号では本格的な震災特集が組まれた。グラビアでは「津波―4人の視点」として、現地を撮影した篠山紀信、平間至、野町和嘉、畠山直哉の作品が掲載され、「総力特集 写真家と震災」では写真家それぞれの被災地との関わりが語られた。震災直後から現地で撮影を続けてきた石川梵やQ.サカマキ、横木安良夫。被災者とその生活に寄り添おうとする今村拓馬、宮下マキ。津波でダメージを受けた写真の復元作業に取り組む高橋宗正。原発事故の見え難い影響を撮影する、岡原功祐や大石芳野などの活動も紹介された。震災に対するスタンスの多様さを伝える誌面となった。

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/120m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)
![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/120m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)
![[連載]アサヒカメラの90年 第13回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/6/7/120m/img_6730dfbf18da117fa17d0746da6ccfa618420.jpg)
![[連載]アサヒカメラの90年 第12回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/4/b/120m/img_4ba46b700feb3876758eae46e548be1f29863.jpg)






























