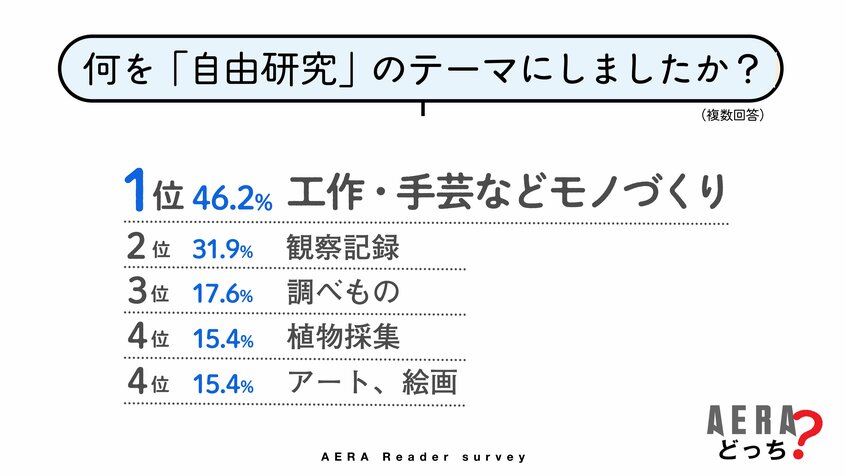
「モノづくりが好きで工作や縫い物等は自由研究とは言えないのでは?と思っていた。小6の時、3歳児等身大の人形(リアルではない)を作り、クラスで話題になって嬉しかった記憶がある」(60代、女性)
「やることがわからなくて、仕方なくゴキブリを観察したら姉妹に笑われてバカにされて大人になってもしばらくバカにされていた」(50代、女性)
「毎日の雨の量を測る。決まった場所に牛乳瓶を置いて、夕立が降った時間とその瓶の中の雨水の水深を測る。毎日家にいることが必要だった。だいたい夕立があり忙しかった」(60代、女性)
「たぶん小5のとき。暑中見舞いのはがきに書かれていた住所がにじんで虹色だった。水性の黒インクが、水に濡れると虹色になるのが不思議で、そのことを調べた。いろいろな黒インクを濡らしてみたが、さまざまな色に分かれた。結果、それは『クロマトグラフィ』と呼ばれるということを知った」(40代、女性)
「今から60年前の小学校4年生の時。当時は、郵便が到着するのが遅かったのか、各都道府県に手紙を送り、到着した日時を返信してもらった。どの自治体も丁寧に手紙を付けて返してくれたのが、とても嬉しかった」(60代、男性)
また、当時の自由研究が、「その後」に影響したと振り返る方も。
「タッパーやチューブなどを使ったヘロンの噴水作りの実験。父親の全面協力のもと工作し、完成したときは本当に嬉しかったし、永久機関の仕組みがとても興味深かった。この頃から物理学が好きだったのかもしれない。最終的には物理学科の修士まで行きました」(40代、女性)
「アメリカシロヒトリの研究をして、家中に毛虫がはっていました。成長の観察記録を細かくつけて、害虫駆除にもつなげ、科学研究県大会にも出場できました。その時の取り組む姿勢が、今も役に立ってます」(60代、女性)





































