デザインはデザイナーだけのものではない時代に

Figmaが普及した背景には、社会全体の大きな流れもあります。日本でも「デザイン経営宣言」が打ち出され、デザインを企業価値向上のための重要な経営資源として活用する経営や事業開発に取り入れることが推奨されるようになりましたが、私たちも日々さまざまなプロダクトを企業と開発するなかでその需要を肌で感じます。すぐれた顧客体験をいかに生み出すかが、企業の競争力に直結する時代です。
加えて、生成AIの登場はプロトタイピングのハードルを一気に下げました。これまでならデザイナーが専門的なデザインソフトを使って何日もかけて用意していたプロトタイプが、いまではAIを活用すれば短時間でかたちにできます。こうした変化を受けて、ビジネス担当者自身がAIやノーコードツールを使ってアイデアを可視化し、そのプロトタイプをもとに議論を進めるといった動きも一部で見られるようになってきました。
ただ、その一方で「誰でも作れるようになったからこそ、『何を作るか』という根本の体験設計がこれまで以上に重要になった」とも言えます。ツールの使い方は簡単でも、体験全体の設計を考えずに進めれば、一見それらしく見えても、本質からずれたプロダクトになってしまう危うさがあります。
だから、デザインプロセスが開かれたということは、今までデザイナーが持っていた視座をビジネスマンも持つべきという時代とも言えるのです。
UX的な考え方はどうすれば身に付けられるのか?
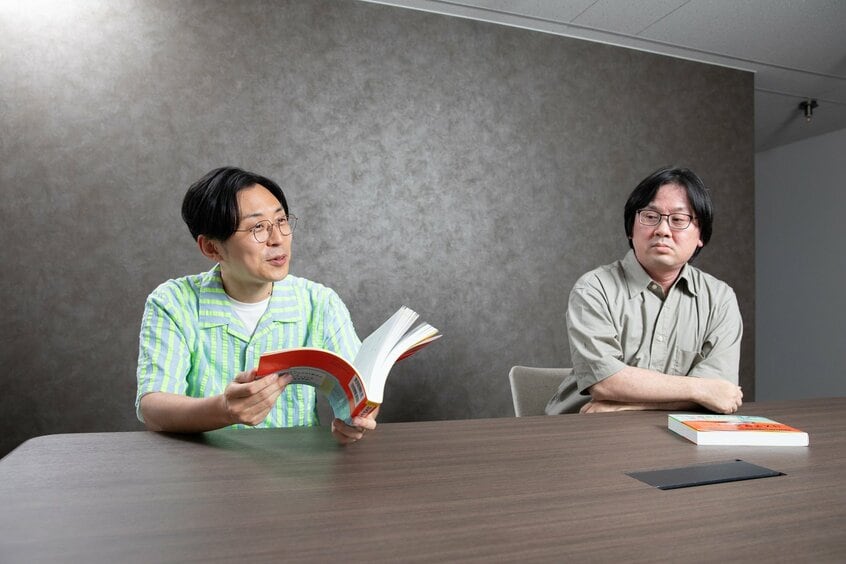
UXとはユーザーエクスペリエンス、つまり「ユーザー体験」の略です。それを設計しようとする試みがUXデザインです。UX的な考え方とは、決して特別な才能やセンスを必要とするものではありません。むしろ、日常の仕事のなかで意識して取り組むことで、誰でも習得できるスキルです。このUI/UXの考え方を誰でも学べるようにしたいと考え、今回『FigmaではじめるUXデザイン入門:アイデア発想から実践まで、デジタルプロダクト制作のためのワークブック』を発行いたしました。
本書のなかで詳しく記していますが、まず第一に大切なのは、顧客の行動を「徹底して観察すること」です。プロダクトを使っているユーザーが、どのような場面でつまずくか、どの瞬間に迷いを感じているかをじっくり観察します。特別な設備は必要ありません。たとえば、顧客が自社のサービスやプロトタイプを使う様子を、少しの間じっと見てみる。それだけでも、多くの気づきを得ることができます。





































