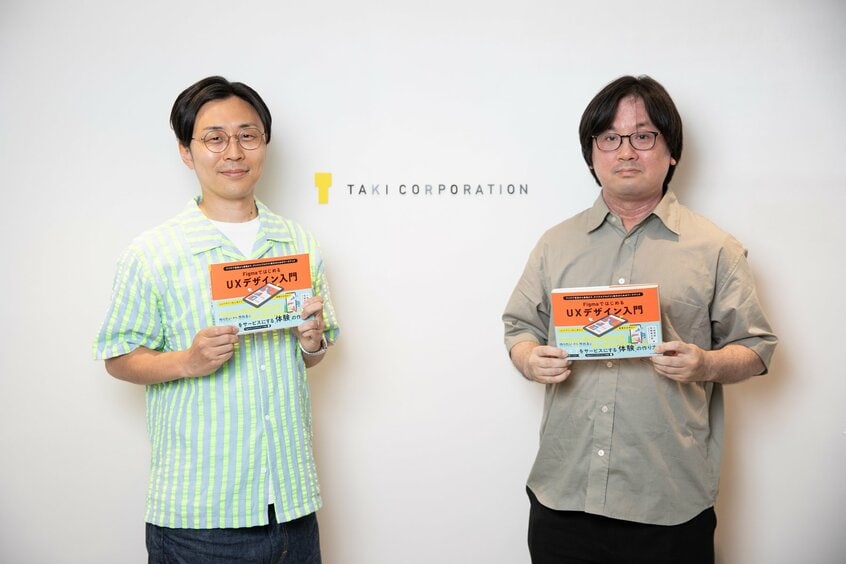
さまざまなデジタルプロダクトの現場で広く使われているツールがFigma(フィグマ)。最近はIPOでも話題になったFigmaですが、デザイナーはもちろん、開発者、企画担当者まで、さまざまなポジションの人々がチームで制作をしていく際に役立つツールです。そして、その際に重要なのが、UXとUIの考え方。
『FigmaではじめるUXデザイン入門:アイデア発想から実践まで、デジタルプロダクト制作のためのワークブック』を発行した株式会社たきコーポレーションの小林秀彰、宮﨑俊太郎両氏に、Figmaの使い方、そしてユーザー体験と向き合うために必要な方法をうかがいました。
* * *
なぜいまFigmaが注目されているのか?
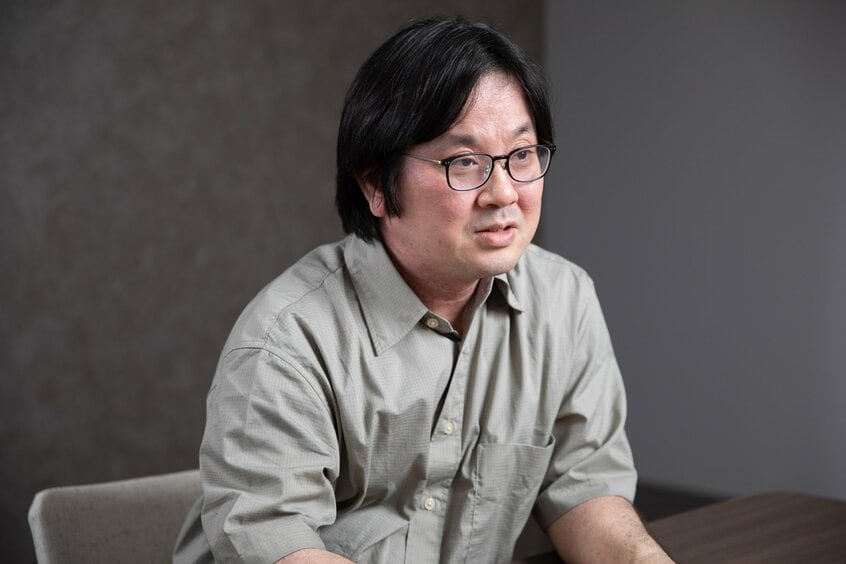
今や多くのテック企業に採用されているデザイン向けコラボレーションツール・Figmaですが、デザインツールにすぎないFigmaがなぜこれほど注目されるのでしょうか。その理由は大きく2つあると私は考えています。
1つはそのニュース性です。2025年7月、米国企業Figma社はIPOの申請書類を提出し、今年最大級のIPOになることが期待されています。2022年にはAdobe社によるFigmaの買収計画が報じられ、結局実現しなかったものの、大きなニュースになったこともありました。
2つ目は、その利便性です。Figmaは「コラボレーションデザインツール」をうたっており、クラウドベースで同じ画面を複数のメンバーがリアルタイムに編集できます。コメント機能を使えば議論の経緯も残り、チームが「なぜこのかたちに決まったのか」を共有できます。アイデアの議論ができるホワイトボード機能もよく使われますね。さらには生成AIによるプロトタイプ機能があり、エンジニアはFigmaのデザインデータから必要なコードを書き出したり、参照したりすることができます。似たような機能を備えたソフトは他にもありますが、Webやアプリなどのデジタルプロダクトを作る機能に特化していることが特徴と言えるでしょう。
このように、デザインプロセスを開かれたものにし、デザインの専門家だけが参加するものではなく、チーム全体のあらゆる職種の人が参加できるようにするという思想の基にFigmaは作られています。これはまさに、昨今の潮流に合っているのです。





































