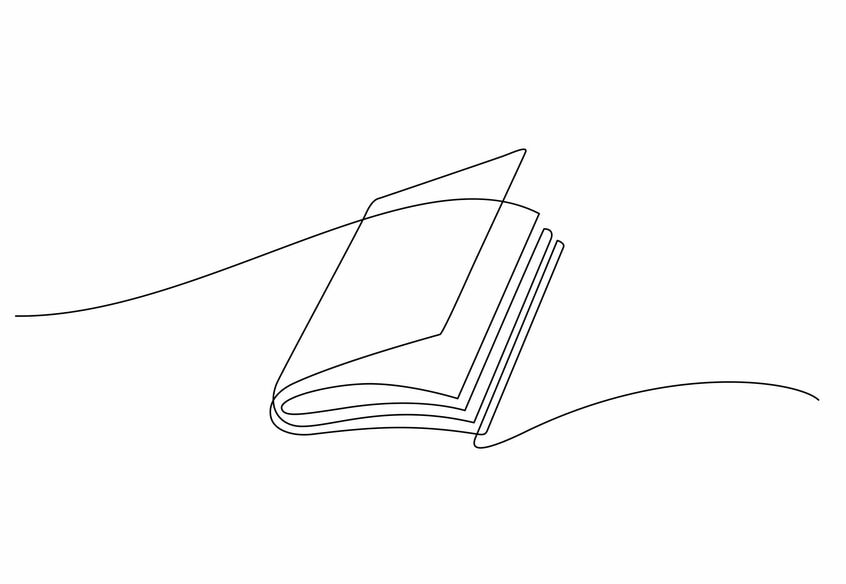
二冊を行き来して考えるうち、私にはいよいよ感じられてくる。谷川俊太郎という詩人にとって、沈黙は言葉と対立し、言葉を切断するものではなかった。沈黙の泉からこぼれ落ちる、ひと筋の水のような存在こそが、彼の見つめる言葉だったのではないかと。
70年以上にわたり、彼は自身のからだを通じ、したたる言葉を書き記した。だがその詩は人間の型に縁取られた、大なるものの断片にならざるを得ない。しずくの源流である沈黙に、どこまで近づいてゆけるのか――。詩人においてその問いは、常に「切実な主題」にほかならなかったのだろう。『行先は未定です』のなかにある親友を悼んだ詩が、彼のながい旅路を示している。
〈本当はヒトの言葉で君を送りたくない 砂浜に寄せては返す波音で 風にそよぐ木々の葉音で 君を送りたい〉(「大岡信を送る 二〇一七年卯月」から)
昨年11月、谷川さんは世を去った。同書で新たに加わった「しぬ」の章に、亡くなる2週間前の言葉が刻まれる。
〈死ぬっていうのはどういう感じなのかな 想像してみるんだけど、困ったことに死んでみないとわからないんだよね〉
これらの二冊には、沈黙へと歩む詩人の最後の息づかいと、去りゆく地表に手向けた畏敬がこめられている。彼と彼の言葉たちにとって、それは穏やかな帰郷であったのだと、私には思えてならない。

行先は未定です

今日は昨日のつづき どこからか言葉が







































