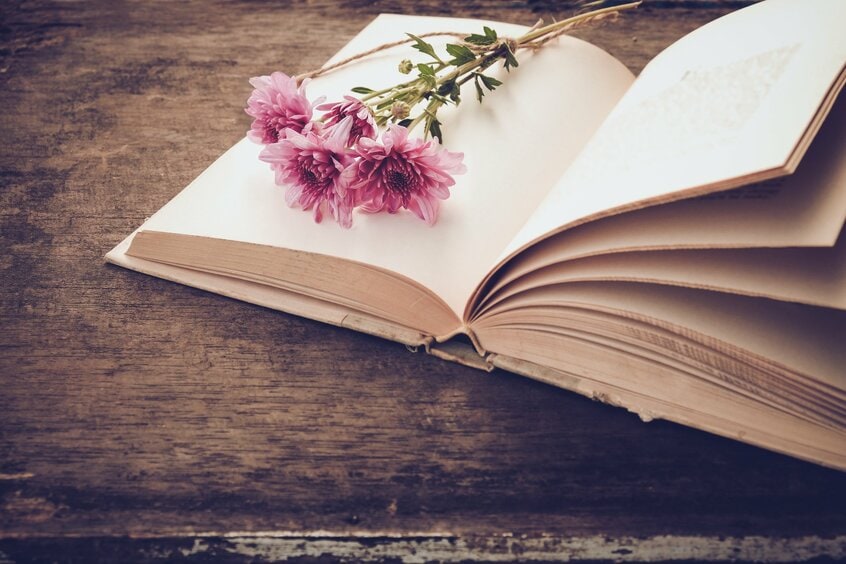
去年逝去された、詩人・谷川俊太郎さんの著書『今日は昨日のつづき どこからか言葉が』『行先は未定です』。谷川さんの担当記者を務めた山本悠理さんが、この二冊を手に谷川さんとの日々を思い返す。
谷川さんが「言葉」に感じていた、物悲しさ。沈黙と言葉の関係。谷川さんにとっての「死」と「詩」。
言葉と向き合い続けた谷川さんが残した数々の詩。そこから何を受け取ることが出来るのだろう。
* * *
沈黙の泉からこぼれ落ちる、ひと筋の水
『今日は昨日のつづき どこからか言葉が』
『行先は未定です』 谷川俊太郎 著
「沈黙は私にとって切実な主題です」
彼が残した言葉の意味を、いまも考えている。
当時、私は現代詩の担当記者として、谷川俊太郎さんの作品を月に一度、受けとっていた。あるとき、谷川さん自身からメールで送られた詩編に添えられていたのが、そのひと言だった。
谷川さんの詩は、いつも静かだ。表層的な無音なのではなくて、私たちが人界で触れているものの奥底を流れる、大なるものにつながる静謐。1952年の第一詩集『二十億光年の孤独』から70年あまり、そうした銀河の轟々たる静けさは、彼の言葉をつらぬいてあるものだった。
しかし、不思議にも思えた。なぜ谷川さんは、膨大な言葉を紡ぎながら、その対極にある沈黙を「切実な主題」として追い求めたのか。あるいは、かくも沈黙を恋慕しながらなお、言葉をさがし続けたのか。
そこに一つの答えを出すことはできない。けれども『今日は昨日のつづき どこからか言葉が』と『行先は未定です』の二冊が、私に示唆を与えたことは確かだ。
どちらにも、谷川さんの最晩年の足跡が刻まれる。前者は朝日新聞で毎月おこなわれた連載「どこからか言葉が」から、最後の4年間の詩編を集めたもの。後者は昨年の春にデジタル配信されたインタビュー集「谷川俊太郎 未来を生きる人たちへ」を加筆・再構成したものだ。
読者として頁を開くと、それぞれが私にとって大切な記憶を呼び起こしてくれる。



































