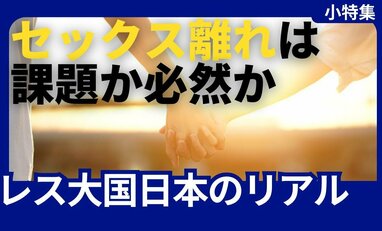恐竜研究に特化した国内初の「恐竜学部」が福井県立大学に今年度開設された。福井県は日本有数の恐竜化石の発掘地。学部長と、狭き門を突破し入学した1期生に話を聞いた。
* * *

「恐竜は福井県が誇るコンテンツ、ブランドです。新しい恐竜学を確立して、ブランドをさらに強化したいと考えています」
そう語るのは今年4月、福井県立大学に新設された「恐竜学部」の学部長・西弘嗣教授だ。2018年に学部新設の構想を発表した当初から注目を集めていた。
福井県は日本有数の恐竜化石発掘地として知られる。国内で発見された恐竜化石の多くが福井県で見つかっているという「恐竜王国」だ。中でも勝山市では新種の恐竜の化石が多数出土し、フクイサウルスやフクイラプトルといった県独自の恐竜も発見されている。2000年に開館した福井県立恐竜博物館は、入館者数が年間100万人を超える人気の博物館だ。「福井県=恐竜」のイメージは広く定着している。

恐竜学部の人気は高く、1期生を募集した一般選抜で、前期日程の倍率は7.3倍、後期日程の倍率は27.3倍と狭き門だった。学校推薦型選抜などと合わせ、男子17人、女子17人の計34人が入学した。
具体的に何を学ぶのか。西教授はこう話す。
「学生は1年次から発掘現場での実習に出まして、3年次には連携協定を結ぶタイでの発掘もあります。ただ、恐竜に特化した研究というイメージが強いですが、学んでほしいのは古生物学だけではありません。日本は災害が多く、さらに地球全体では温暖化も課題です。災害復興や防災、自然再生といった観点で、自然科学の知識を身に付けることは非常に重要になっています。生物、地質に測量と幅広く学び、自然にかかわる人材を育成したいと考えています」

今はどの学問分野でもデジタルの活用が必須。大型CTスキャンによる化石のデータ解析などを通して、最新のデジタル技術に優れた人材育成を視野に入れる。
恐竜博物館との連携も目玉
さらに隣接する恐竜博物館との連携も目玉の一つだ。
「博物館の研究員や学芸員が授業を行い、学生の研究成果は博物館に提供、展示する予定です」(西教授)

新入生の多くは恐竜に高い関心を持って入学した。武生高校(福井)から学校推薦型選抜で合格した城戸良太郎さんは、小学校低学年のころから恐竜に夢中だった。
「祖母が恐竜博物館に連れて行ってくれたり、図鑑を買い与えてくれたりして、恐竜の絵をよく描いていました。最初はただ『かっこいいな』というだけでしたが、恐竜は知れば知るほどわからないことが増えていくんです。自然と未知なる部分を研究したいと考えるようになりました」

5月から始まる予定の発掘実習を心待ちにしている。
「入学後に大学からハンマーとヘルメットの購入を指示されて、『あ、発掘用だ!』とワクワクしました。今のところ実際に購入したときが『恐竜学部に入学したんだ』と一番実感できた瞬間ですね」
将来の夢は恐竜研究の学芸員だ。
「一番好きな恐竜はスピノサウルス。復元図が目まぐるしく変わるという特徴的な恐竜なので、ぜひ研究したいです」