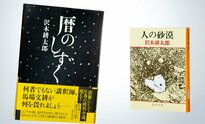「インクルーシブ」「インクルージョン」という言葉を知っていますか? 障害や多様性を排除するのではなく、「共生していく」という意味です。自身も障害のある子どもを持ち、滞在先のハワイでインクルーシブ教育に出合った江利川ちひろさんが、インクルーシブ教育の大切さや日本での課題を伝えます。
* * *
4月後半になりました。今年度から新生活が始まった方はそろそろ新しい環境に慣れた頃でしょうか? 我が家の双子の娘も3月に高校を卒業し、医療的ケアが必要な長女は平日は生活介護施設へ通所、次女は大学へ通学しています。どちらも4月1日から新生活がスタートし、楽しく通いつつもゴールデンウイークでの休息が待ち遠しいようです。
今回は、我が家の双子の娘たちの新生活について書いてみようと思います。
ごく自然に家族の話をできる環境
4月1日。夫とともに、次女の大学の入学式に出席しました。幼稚園から高校まで一貫校で過ごした彼女にとって、知っている人がいない環境に入ることはとても珍しく、緊張したのではないかと思います。さらに、今までは自宅から徒歩10分の距離だったのが、乗り換えを2回して1時間半以上かけて通学することになります。この日は雨が降って冬のように寒くなり、余計に通学への不安が増したように見えました。ところが、翌日からどんどん友達ができ、我が家の近くから通っている人がいることもわかり、あっという間に大学生活に慣れたようです。
医療従事者を目指す学部に進学したため、興味があることが似ているのも過ごしやすい理由のひとつかもしれません。健康診断では教授が学生の採血をし、腕を縛る理由を聞いたり、注射器を刺す瞬間の針の角度を見ているようにと言われたりしたとのこと。そんな話をしてくれる次女はとても楽しそうでした。小学生や中学生の頃には、自分が双子であることや寝たきりの長女のことを周りにどう話せば良いのかと、きょうだい児ならではの悩みもありましたが、医療者になる環境の中では、ごく自然に家族の話をすることができたようで安心しました。