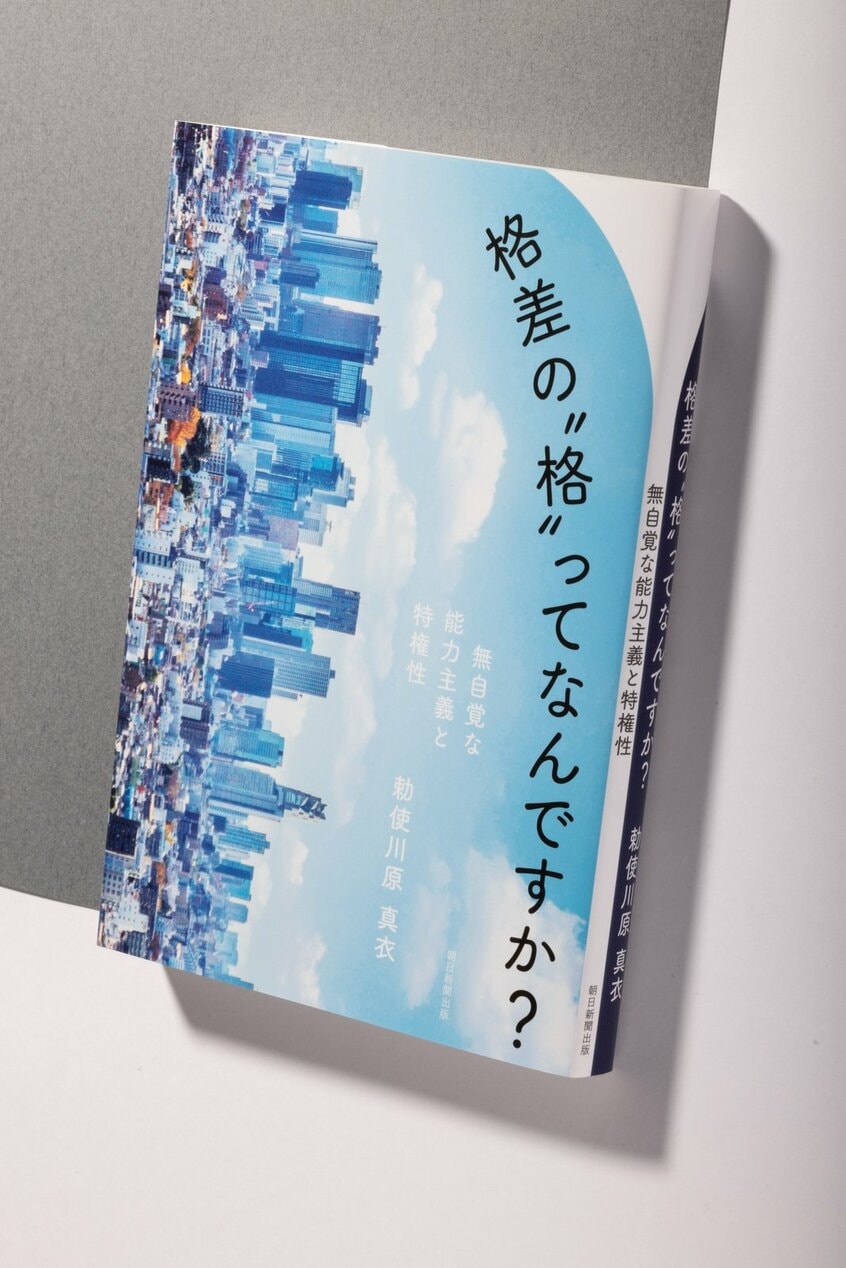
「場の空気を読んで調整することも能力とされ、和を乱さないことが求められると、『ちょっと待ってください、考えさせてください』と言いにくくなります。でも、それは個人の問題ではなく、学校や家庭教育の中で求められてきた構造の結果とも言えます。言えない自分を責めると泥沼化し、言い出せることすら能力とされてしまう。でも、ただ真面目に教えを守ってきたからこそ言いにくかっただけで、『本当はおかしい』と思うことこそが『岐路』ではないでしょうか」
そうは言っても、違和感を覚えても言い出せない。「岐路」で立ち止まることができないと言う人はぜひ「未熟上等!」という言葉を心に刻んでほしい。
「『何ができるか』ではなく、『いてくれてありがとう』と言われる経験が大切だと思います。だからこそ、『謝意から始める組織づくり』が必要なんですよね。『できるから居場所がある』のではなく、そもそも人は自分の意志で生まれてきたわけではない。だからこそ、『すでに在ること』をもっと大切にしてほしい。人材を精鋭化しようと選抜し、人を序列化するほど、多様性を認めにくくなります。でも、人口減少・労働力不足の時代に、これ以上精鋭化を進めてどうするのでしょう? これから必要なのは、能力を競わせることではなく、それぞれの強みを生かし合うこと。掃いて捨てるほど人がいた時代はもう終わったのだから」
ただ、実は話はそんなに簡単ではない。何故なら勅使川原さん自身が一貫して、簡単にわかった気になることを避けているからだ。違和感をなかったことにせず、表明し、考え続ける。それを各々がし続けることこそが、「誰もが生き合える社会」への道なのだろう。
(ライター・濱野奈美子)
※AERA 2025年4月21日号









































