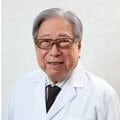「本人が『病院からお家へ帰りたい』と言っても、家族が『在宅でいいよ』と言ってくれるのは、僕の感覚ではおよそ5%。そういう恵まれた患者さんが僕の診療所に来る。だから、家に戻ってこられただけで100点なんです」
萬田医師は診察時間は毎回1時間かけて、患者と家族との対話を重視する。そういったコミュニケーションから言いにくいことを言える信頼関係が築かれ、タブー視されがちな「死」を口にするときも、笑いに変えていく。そして、「体にいいことより、心にいいことを」と患者に呼びかけ、患者のやりたいことを実現させてあげようと心がける。萬田医師の診療は「心をケアする対話」でもある。
「正直、撮影を始める前はここまで面白い先生とは思っていませんでした。ただジョークが面白いだけではなく、笑いの力で患者の心を明るくすることを生きがいのようにしている。(まるで落語の名人芸。)これこそが萬田流在宅緩和ケアなのだと感じました」(オオタヴィン監督)
映画には萬田医師の診療を受ける5つの家族が登場するが、実際に取材をした家族は3倍近くあったそうだ。撮影を始める前は、患者や家族との撮影交渉が難航すると予想された。
「『この映画に出て良かった』と言ってもらえる作品を作りたくて、撮影していく中で、快く出ていただいたのが5つの家族だったということです」

家族が別れを受け入れていく様子も
当初は自宅で生き生きと過ごす姿を撮れれば十分と考えていたそうだが、結果的にお別れまで撮影することになり、家族が別れを受け入れていく様子も描かれる。作中で母を看取った娘は言う。
「『がんが一番別れる時間をくれる病気なんだよ』と萬田先生が言っていましたが、『がんが一番いいわけないだろう!』と思いながらも、母を看取ることができたとき『あ、このことだったんだな』とわかりました」
ドキュメンタリー映画だからこそ、患者、家族の表情まで届けられ、萬田医師との信頼関係も伝わる映画となっている。オオタヴィン監督はこう話す。