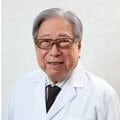治る見込みがないと宣告されたがん患者の多くは「自宅で自分らしい生活を送って最期を迎えたい」と願う。しかし、それをかなえられる患者は数少ない。その背景に、「在宅緩和ケア」という選択肢が正しく知られていないことがあるのではないか――。そんな考えのもとに撮影されたドキュメンタリー映画『ハッピー☆エンド』が、4月18日から全国順次公開される。萬田緑平医師と在宅緩和ケアを選択した5つの家族を追った映画だ。オオタヴィン監督に製作の意図などを取材した。
* * *
がんで余命宣告を受けた患者が病院での治療を受けないことを選択して、自宅で緩和ケアを受けることに――。この状況から、どんな患者の姿をイメージするだろうか。もし「ベッドで寝たきりの患者を家族が必死に看病する」光景を浮かべるとしたら、このドキュメンタリー映画に登場する患者の姿によって、その先入観は覆されるだろう。
がんが進行し、治療しても根治が見込めない状態といっても、すぐに寝たきりになるわけではない。緩和ケア医にがんによる痛みなどをコントロールしてもらえば、それまでとほぼ変わりない生活を送ることができる。「在宅緩和ケア」とは、心と身体の苦痛をやわらげ、自宅で自分らしい生活を送れる治療法なのだ。そして、病院で宣告された余命より、長く生きるケースもあるという。
この映画で映し出されるのは、在宅緩和ケアを選択し、思い出作りの家族旅行、大好きなゴルフやお酒など、残された時間を自分らしく生きる人たちだ。そこには、余命宣告を受けた患者としてよく描かれる「苦痛」ではなく、「笑い」がある。

オオタヴィン監督はこう話す。
「在宅緩和ケアの映画というと、つらい闘病や悲しい終活をイメージされるかもしれませんが、この映画はその対極にあります。患者が自分らしく生きることでそこに幸福感がある『笑い』が生まれるということを伝えられたらと思っています」
映画作りのきっかけは、監督の母の死だという。温泉旅行に行っているときにピンピンコロリで亡くなった。