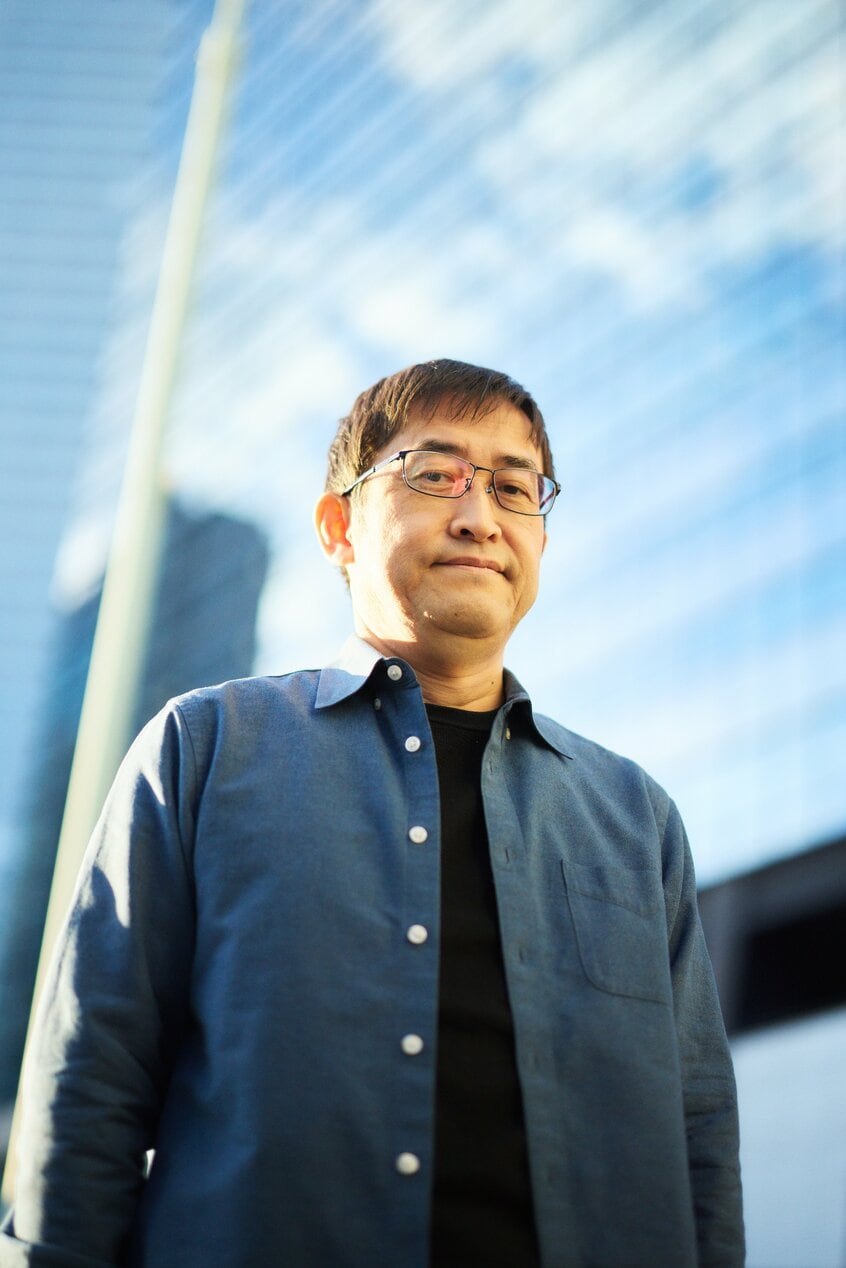
なぜ伊藤作品はそこまで人気なのか。世界で唯一日本の漫画に特化した専門誌「ATOM」の創刊者でアングレーム国際漫画祭アジアプログラム・アート・ディレクターのフォスト・ファズロさん(42)は話す。
「海外で人気のある日本の漫画は『NARUTO』や『ワンピース』など作品名で認知されることが多いんです。でも伊藤さんは『伊藤潤二』という名前自体がブランドでカルト的な人気を持っている。そこが他の漫画家との圧倒的な違いです」
伊藤作品の魅力を「見たこともない絵の美しさと繊細さと相反する暴力性、ストーリーのおもしろさはもちろん、敷居が高くないところ」と分析する。
「伊藤作品はアート(芸術)でありながら難しくない。短編作品が多く誰もが手に取りやすく、ある意味でわかりやすく大衆的なのです」
世界共通の「文法」
伊藤さんもうなずく。
「短編はより純粋で『純度が高い恐怖』が描きやすいのです」
思いついたアイデアを現実の世界に落とし込むためにはどうすれば奇想天外すぎず「本当に起きるかもしれない」と読者に思わせるかがキモだ。短編だとそれがやりやすいと伊藤さん。
「長編になると恐怖だけでなく、人間関係などエピソードを広げる必要がありますが、短編にはシンプルに恐怖を盛り上げてクライマックスへと進むストレートさがある。スノードームのように『こういう世界ですよ』と完結した小宇宙のなかに閉じ込めてしまうことによって物語が成り立つ、みたいな感じです」
さらにその恐怖が世界共通であることも重要だ。前出のフォストさんは言う。
「伊藤さんには『恐怖』に対する世界共通の文法があり、誰もが共感できます。恐怖とは突き詰めれば『死』だと私は思います。自分が存在しなくなることへの恐怖。自分がコントロールできないものへの怖さ。伊藤さんは読者が求める恐怖とは何か、どうすればそれを体験させられるかを第一に、真摯に考えてくださる方なのです」
北米を中心に伊藤作品の翻訳・販売を手がけるVIZ Mediaの営業担当ディレクター、サラ・アンダーソンさん(50)も言う。
「伊藤先生の作品は自分をホラーファンだと思ってもいない人たちにも人気があります。私もその一人で、ホラー映画なんて怖くて絶対に観られません!(笑)。でも伊藤作品は絵がとても細密で文字と完全に調和しているので、いつの間にか引き込まれてしまうんです」




































