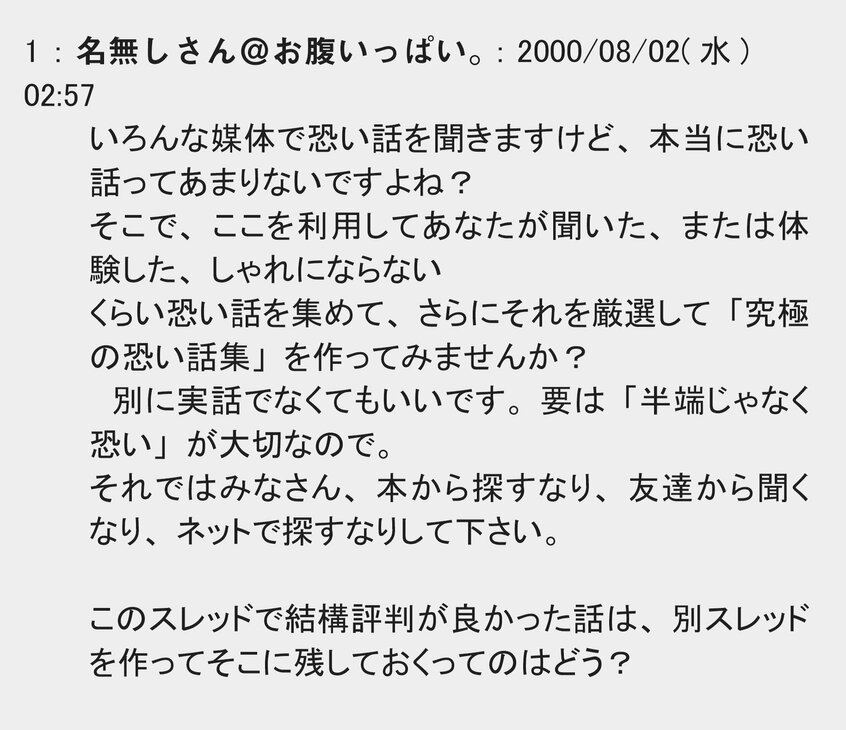
企画展や小説、映像作品など、ホラー系コンテンツが話題を集めている。『ネット怪談の民俗学』著者・廣田龍平さんは、近年の「怖い話」の盛り上がりをどう見るのか。AERA 2025年2月24日号より。
* * *
この21世紀に「怖い話」が最も多く生まれている場所はどこか。それはネット上かもしれません。いわゆる「ネット怪談」。台頭してきたのは1999年、匿名掲示板「2ちゃんねる」に「オカルト板」が登場した頃からです。書き手も読み手も「同じ場所」にいて、投稿を考察したり、「似た話を聞いた」と話を膨らませたりリアルタイムで反応しながら、怪談が共同構築されていくようになります。
2000年にはその代表的なスレッド「洒落にならないくらい怖い話を集めてみない?(洒落怖)」が立ち、「くねくね」などの作品が生まれます。他にも2ちゃんねるでは「コトリバコ」など田舎の村での怪奇現象を描く「因習系」や、「きさらぎ駅」など知らない場所に行ってしまい戻れなくなるといった「異世界系」の怪談が数多く生み出されました。携帯端末の浸透により、怪異に巻き込まれた状況を当事者が逐一報告する「実況型」も増えていきます。
2010年代になるとSNSの普及で画像付きの怪談が、10年代後半から20年代にかけては動画によるものが登場。テキストによる「物語」は省かれ、「何かやばいの映ってる」といった「不穏さ」を伝えるものが一般化していきます。
昨今のホラー作品では、虚構の物語を事実のようにドキュメンタリー風に構成する「モキュメンタリー」が流行です。その怖さが自分の現実とどこか地続きであることを求めるものが増えている。私はそこに、書き手と読み手が同じ場所にいて物語を共同構築し、実況によって同じ時間も共有するネット怪談、とくに2ちゃんねるにおいて醸成された感性を感じます。
(編集部・小長光哲郎)
※AERA 2025年2月24日号




![AERA (アエラ) 2025年 2/24 増大号【表紙:富江(伊藤潤二 描き下ろし・蜷川実花 背景写真)】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CfyXVHznL._SL500_.jpg)





































