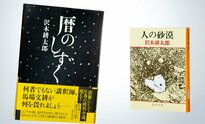小中高と大分の公立校で学び、米・ハーバード大学、ジュリアード音楽院を卒業・修了したバイオリニストの廣津留すみれさん(31)。その活動は国内外での演奏だけにとどまらず、大学の教壇に立ったり、情報番組のコメンテーターを務めたりと、幅広い。「才女」のひと言では片付けられない廣津留さんに、人間関係から教育やキャリアのことまで、さまざまな悩みや疑問を投げかけていくAERA dot.連載。今回は、40代女性からの「友だち」に関する質問に答えてもらった。
* * *
Q. 大人になってから、どこからが知人でなく、友だちなのか、よくわからなくなってきました。仕事を通じて仲良くなった人を「友だち」と呼んでいいのかも迷いますし、友だちになりたいと思ってもどうしたらいいかわかりません。廣津留さんにとって、「友だち」とはどんな関係や存在のことを指しますか?
A. たしかにその気持ち、わかります。個人的には、高校や大学時代からの友だちで、今も仲がいい人たちは明確な「友だち」ですね。私の場合、学生時代の友人の紹介で知り合った友だちも多いのですが、彼らもはっきりと「友だち」と呼べると思います。仕事仲間か友だちかの線引きは、自分や相手のタイプにもよるのかなと思いますね。私はコミュニケーションが好きなほうなので、仕事相手でも同じようなタイプの人たちとは仕事終わりにごはんに行ったり飲みに行ったりするんです。コミュニケーションを重ねていくうちに腹を割って話せるようになるからだんだんと友人になっていくけど、仕事とプライベートを完全に分けているタイプの人とは、仕事以外でそうやって話せる場をなかなか持てないですよね。そうすると、どんなに仕事の相性が良くても「仕事仲間」でいる気がします。それはそれではっきりしていて良いかと。
「友だち」の定義……、難しいなあ。うーん。私にとっては「困ったときに味方になってくれる、頼れる人」かな。仕事以外のことでも。学生時代からの友だちは昔の自分も知っているから、よほどのことがない限りは味方でいてくれそうだなという安心感があるんですよね。
それくらい仲良くなるにはそれなりの期間が必要だと思うから、大人になるほどできにくくなりそうですが、気が合う「友だち」は年齢に関係なくずっと作り続けられると思います。友だちになりたいと思う人に出会ったら、会う頻度を上げてみてはどうでしょう? 学生時代は毎日のように会うから自然と仲良くなりますよね。逆にこの人とは仲良くなれなさそうだということも、顔を合わせているからわかること。やっぱり会わないことには、その人との相性はわからないし、仲良くなるきっかけもないと思います。
会うことは、友だち関係を維持することにもつながります。私は演奏活動などでいろんなところに行く機会があるから、「今度〇〇に行くんだけど会わない?」と、各地にいる友だちに連絡をとって会うきっかけもあります。特にアメリカに住んでいたときは、年2回くらいのペースで帰国していたので、その都度日本で友だちに会えました。いまは日本を拠点にしながらニューヨークに年1回は必ず行っているので、向こうにいる友だちにスケジュールを送って会える人とはできるだけ会っています。年1回でも顔を合わせていないとだんだん疎遠になってしまうし、定期的に会うことで、自分の変化も見直せるような気がします。
おもしろいのが、ニューヨークの私の友だちは「今日、空いている?」と急に誘っても会ってくれることが多いけど、日本の友だちは「3週先で」など、先の日付になることが多いんです。もちろん人によりますが。友だち同士であってもきっちり予定を組みたいというのは、几帳面な国民性なのかもしれないですね(笑)。
構成/岩本恵美 衣装協力/BEAMS