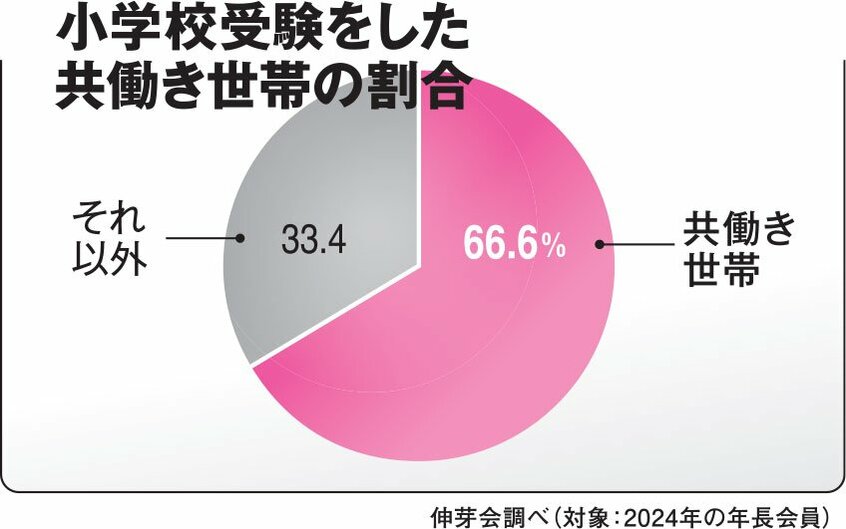
自身は中学受験の経験者。長男の小学校受験は「あまり考えていなかった」というが、教育熱心な家庭に育った夫からの提案を受けて、小学校受験をすることにした。
受験のための教室は、大手と地元の二つに、2年間通わせた。大手は情報収集や模試のために利用した。地元の教室は、高い合格率で知られるところを選んだ。
「年長になってからは平日も教室通いになったので、仕事をしながら保育園への迎えと教室への送迎をこなすのが大変でした。でも、夫とうまく分担してやりくりしました」
コロナ禍で仕事がフルリモートになったことにも助けられた。自宅近くに義理の両親が暮らしており、夫婦ともに難しい時はピンチヒッターとして、送迎などをお願いすることもあったという。
ただ、大変なのは送迎だけではなかった。難関私立小学校を目指すとなると、毎日の家庭学習は欠かせない。
「朝、保育園に行く前の30分と、帰ってからの30分。それから、日曜日の午前中は勉強に充てました」
個性に応じた受験の形
ただ、長男は勉強があまり好きなタイプではなく、勉強をさせるのがかなり大変だったと振り返る。
「詰め込み学習もかなり多く、ほとんど無理強いだった気がします。モチベーションが上がらない子どもにイライラして怒ってしまったことも、正直何度もあります」
そんな時は夫の出番。協力と分担で切り抜けた。
「夫が担当の日は私がフリーになれるので、丸1日趣味の登山に出かけたり、ランニングをしたりしてリフレッシュすることができました。夫も教育熱心で、むしろ私より積極的に関わっていたので助かりました」
小学校受験をめぐる体験談を話してくれた3人のワーママたち。それぞれの考え方、子どもの個性に応じた小学校受験の形があったが、共通していたのは、真剣に子どもの将来、幸せを考えている姿勢だった。
(ライター・浴野朝香)
※AERA 2024年12月16日号より抜粋






































