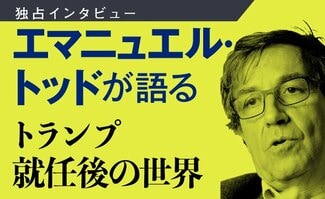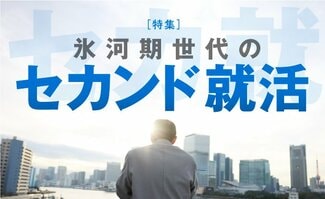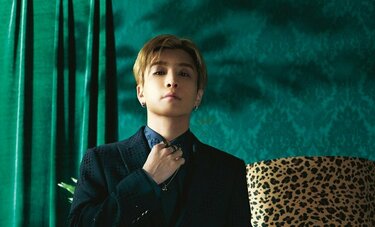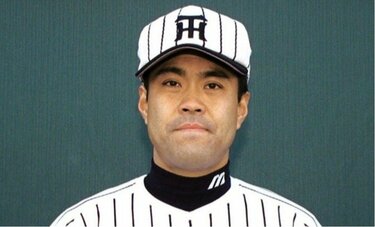5000件に及ぶ片づけ相談の経験と心理学をもとに作り上げたオリジナルメソッドで、汚部屋に悩む女性たちの「片づけの習慣化」をサポートする西崎彩智(にしざき・さち)さん。募集のたびに満員御礼の講座「家庭力アッププロジェクト®」を主宰する彼女が、片づけられない女性たちのヨモヤマ話や奮闘記を交えながら、リバウンドしない片づけの考え方をお伝えします。
【魅惑のアフター】「いつか使う」「いつか着る」で家の中はパンパン 片づけたら暮らしやすくなって体重も減った
case.84 母親の介護をきっかけに暮らしをアップデート 夫と二人暮らし/保育士
人生には、進学や就職、結婚、子どもの誕生など、身の回りの環境がガラリと変わるようなことが起こります。そのたびに自分や家族の生活も変わるので、家の中もあわせて見直すことが必要です。
進学や就職などはある程度予測できて準備もできますが、中には予期せぬタイミングで訪れることがあります。例えば、介護。
息子が独立し、夫と二人で暮らしている恭さんは、母親の病気がわかって通いの介護が始まりました。フルタイムだった仕事を、柔軟に働けるように時間を短く調整。月に1回ほど、遠方にある実家に3~4日滞在する生活が2年ほど続きました。
この間、自分の家のことはいろいろと後回しになり、少しずつ暮らしにくさを感じるように。
「それまでは、片づけはモノを棚とかにしっかり収めていればいいと思っていました。実際、家の中のモノは多くなくて、どこに何があるかをちゃんと把握できていたんです」
ところが、いつからか恭さんは家の中のモノが管理しきれなくなってしまいました。
「あれ、なんでこれがここにあるの?」「同じようなモノがいっぱいある……」
それでも片づけに費やせるほどの時間の余裕はありません。仕事と介護に割く労力が大きくなり、“相方さん”と呼ぶ夫にすべての家事を任せることもしばしば。
「相方さんは、家が散らかり始めていることについて特に何も言いませんでした。私だけが気にしていたのかもしれないですけど……」
通いの介護生活が2年ほど続いた頃、母親が他界します。遺品を整理しているときに、恭さんはふと不安に駆られました。
 西崎彩智
西崎彩智