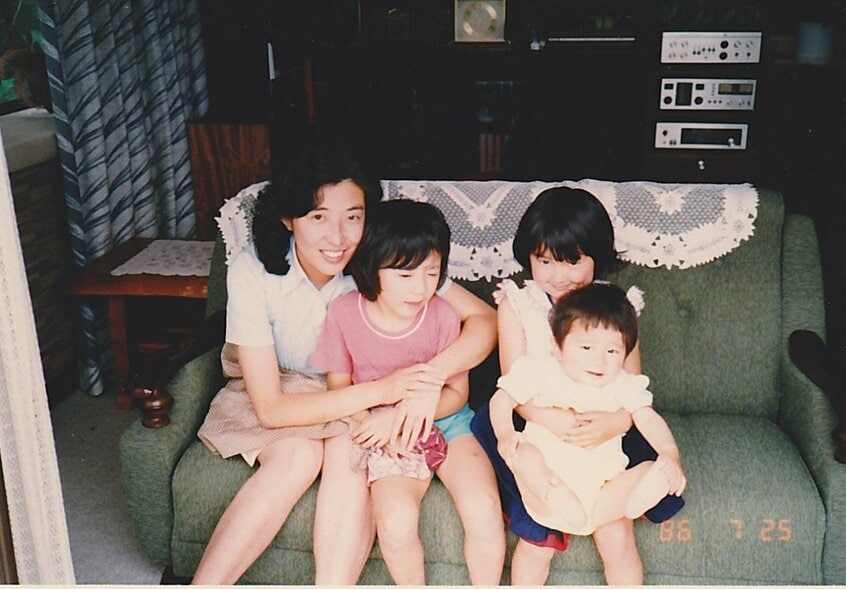
姉はどれほど悔しかっただろうか
2年の浪人生活を経て、医学部に合格。2011年には大学病院の小児科で勤務を開始し、発達障害の診療について学び始めた。
自ら選択した道を突き進んでいた西村さんだが、その時、予期せぬ現実に直面する。
すでに結婚していた西村さんは、12年に第1子となる長男を出産した。その長男が1歳半のころ、ある事実に気が付く。
言葉の発達が遅い。自分と目を合わせない。他の子どもより動き回る……。医師として、長男に自閉症の特性があることを認めざるを得ない状況。だが、その一方で、ひとりの母親として、簡単にその現実を受け入れることはできなかった。
「当時の自分がどんな様子だったのか、まったく思い出せないのですが、夫に聞くと、寝ている長男のそばで毎日泣いていたそうです」
だが、そんな西村さんに転機が訪れる。ひとつは発達支援をする臨床心理士に、長男への接し方を学んだことだ。
ほめ方や、叱り方などについて、使う言葉や態度を少し変えてみるだけで、長男は驚くほど変わっていった。できることが増え、かんしゃくを起こす回数も減った。
もうひとつは、重度自閉症の日常をつづった本がベストセラーになった作家・東田直樹さんの存在を知ったことだ。
東田さんは会話はできないが、文字盤を使って意思表示ができる。その事実に、西村さんは大きな気付きを得た。
「接し方を変えただけで成長した長男もそうですが、言葉を話せない=なにも分からない、では決してないんですよね。話せなかったり、体が上手に動かなくて意思表示ができないだけで、ちゃんと分かっているんです」
思えば、姉こそがそうだった。
違うと思っていても、言葉で表現できない。身ぶりでも伝えられない。主治医から処方された鎮静剤も、嫌だったけど、伝えられなかっただけではないのか。

「勝手に『話しても何も分からない人』にされて、姉はどれほど悔しかっただろうか。分かっていることを分かってもらえなくて、絶望していたんじゃないだろうか。妹なのに、そのことを理解してあげられなかった自分自身にも、悔しさを覚えました」



































