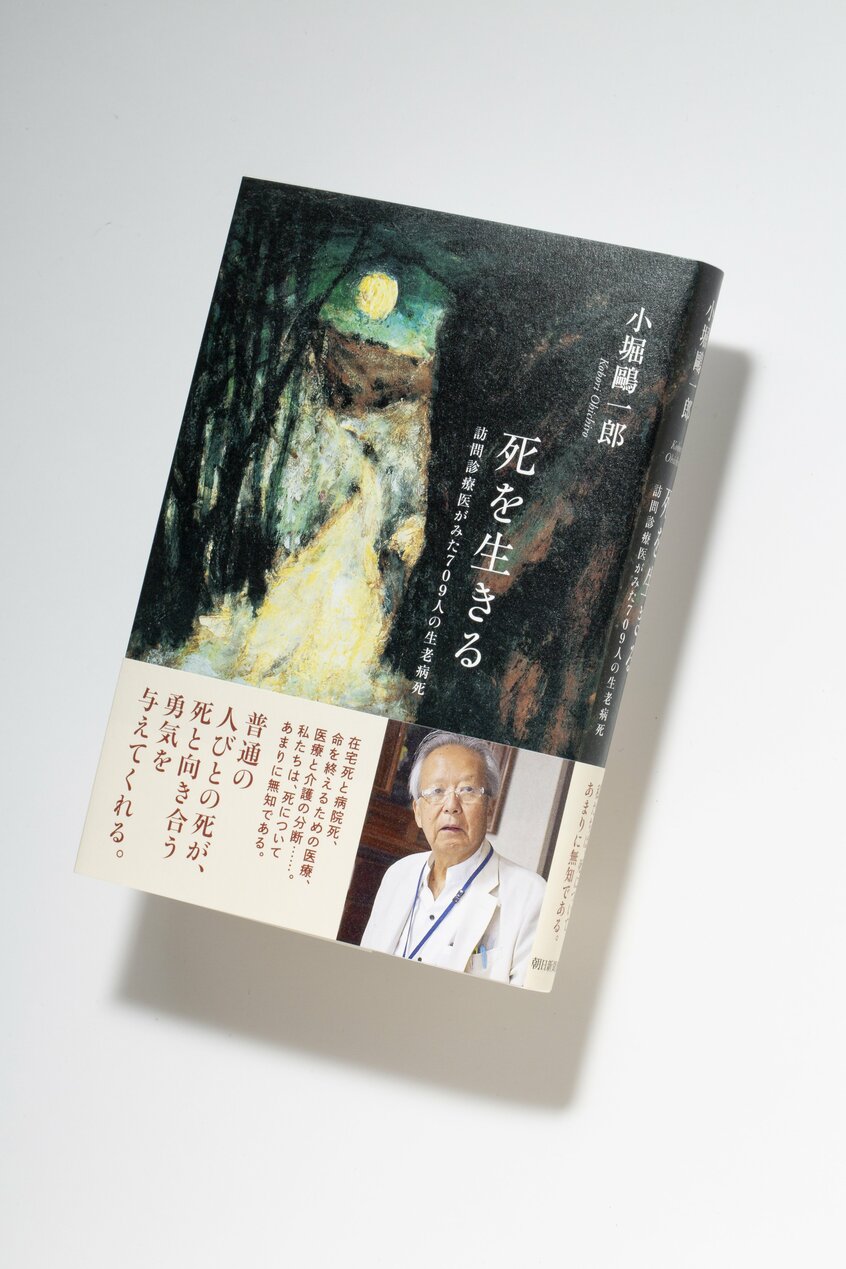
戦前に映画女優として活躍した98歳の女性は自室を自身の全盛期のブロマイドで飾っていた。86歳のある女性は友人女性の病死後に後妻になることを決意した。市井の人々の人生を書き残すこと。それは名前も顔もない人々に顔と声を与える作業だ。さらに「生かすこと」が前提の現代医療への疑問や、高齢化社会に向けての提言もなされる。
「胃がん末期の76歳の男性は酒を自由に飲みたいと、食事もとれない状態から自宅に帰ることを希望した。翌日から彼の枕元にはチューブにつながれたウイスキーボトルがありました。患者のカルミネーション(=最期の望み)について私も模索する日々です」
自分はどんなふうに生き、どんな最期を迎えたいのか。自分を振り返り、家族で話し合う一助になり得る一冊だ。
「有名無名に関わらず人間は誰もが等しく、その人生は素晴らしい。特に介護に携わる人たちに『病人のわがまま』と済まさずその言葉に耳を傾け、誰の尊厳も大事にしてもらえればと願います」
(フリーランス記者・中村千晶)
※AERA 2024年6月17日号








































