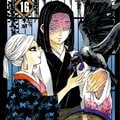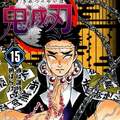87年、THE BOOMは、東京・原宿の「ホコ天」(歩行者天国)でバンド活動をスタートした。当時、「ホコ天」は社会現象ともなり、路上ではおびただしい数のバンドが演奏していた。88年にレコード会社のオーディションに合格し、メジャーデビュー。最初は、ロックにスカやレゲエをミクスチャーしたバンドだったが、沖縄の音階を取り入れた「島唄」が大ヒット。ラテンや南米の音楽をリスペクトし、サンバのリズムに影響を受けた「風になりたい」も数カ月にわたってヒットチャートにランクイン、世界中でカバーされた。
「ラボ・パーティ」の参加が視野を海外に開かせた
宮沢はバンドを率いて貪欲に世界中の音楽を吸収しながら、音楽の方向性を自由自在に変え、旺盛な活動を続けてきた。単に世界の音楽を耳で聴くだけではなく、身体丸ごとをその国や地域や人、文化の中に浸し、音楽家たちと友人になり共に演奏してきた。
「加藤登紀子さんや坂本龍一さん、佐野元春さんのような“旅をしながら音楽を創造する”スタイルに憧れていました」
子どもたちへの語り聴かせなどの小さな集まりでも、呼ばれたら旅烏(たびがらす)のようにひょいと出かけていく。枠にはまらない行動は先達の影響も受けながら、音と言葉を濃密に連動させつつ、異文化に対するリスペクトを真摯(しんし)に深めていった。
山梨県甲府市に生まれた宮沢は、小学生のころから言葉に対する興味が強く、フォークソングブームだった中学2年の頃、自分で作曲を手掛けるようになった。「島唄」のベースとなる沖縄民謡を最初に聴いたのは小学生の頃。ラジオから流れてきた喜納昌吉の「ハイサイおじさん」だった。聴いたことのない音階や歌詞は、多感な宮沢少年に確かな手触りを残した。