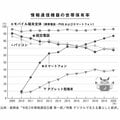私たちは脳の働きでものを見ている。ベッドメリーをじっと見つめる赤ちゃんも同様だ。視認のメカニズムを眼科医・松岡俊行さんの著書「スマホアイ」(アスコム)から紹介する。
* * *
見ることから興味関心が生まれる
みなさんもアンパンマンはご存知だと思います。いつの時代も子どもたちから大人気です。
ところで、なぜアンパンマンはあんなにも子どもたちの心を惹きつけてやまないのでしょうか。一説には、子どもが興味を持ちやすい色と形がその理由ではないかといわれています。
生後間もない赤ちゃんは目の機能が未熟で、6歳ごろまでに発達していきます。この発達の段階で早くに興味を示すのが、色では赤などの明るい暖色系、形では丸型だというのです。まさにアンパンマンは、赤ちゃんが好きな姿形をしていることになります。つまり見えているものに反応し、好きになったり、触れてみたくなったりするわけです。
私たちは、いろいろなものを「見る」ことで、興味が出たり、好奇心が湧いたり、注意を払ったり、集中したりできます。赤ちゃんがガラガラを目で追う。子どもが気になるものを見つけて、「あ!」と声をあげ指でさす。
見えることが当たり前だと、つい忘れてしまいがちですが、目は学習や行動や感動のいちばんの入り口なのです。こうしたことからも、目と脳、そして「見ること」と発達が深く関わっていることが想像できると思います。
デジカメよりはるかに高性能な人間の目と脳
繰り返しになりますが、私たちは目だけでなく、目と脳のセットでものを見ています。網膜から入ってきた信号が、視神経へ送られ、最終的に立体感のある映像として脳が認識することで「見えた」となるのです。
目はカメラのレンズで、脳はパソコンのようなものといえば、わかりやすいでしょうか。