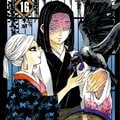大学の大半の学部はジャングル探索型で、その学びは自由だという。たとえば韓流のコンテンツが好きだから国際学部、ゲームビジネスを学ぶために経営学部、VRを使った癒やしを研究するために情報学部を目指す、といったケースも珍しくない。
「進学する動機は柔軟で良い。大学での学びを通じて視野が広がった結果、本当にやりたいことを見つけたり、当初はまったく考えていなかった就職先に進んだりという学生もたくさんいます」
大学は広い地図を見て選んでほしい
「開発途上国の若者が、どうやって大学を探すか知っていますか?」と倉部氏は問いかける。
「世界地図をまず広げるのだそうです。どの国にいって、なにを学ぼうか、と。もちろん、開発途上国の若者は近隣に大学がなく、奨学金を得て世界に出なければ学べないという事情もあるでしょう。でも実のところ、多くの若者が『家から通える範囲』で大学を探しているのは、おそらく日本くらいです。私たちが常識と思い込んできたことも、世界的には『非常識』。家庭の事情もあるでしょうし、日本のすべての若者に世界へ出ろというつもりはありませんが、それでも生徒達にはできる限り広い地図を使って、自分の進路をつくってほしいなと思うのです」
(取材・文/柿崎明子)
くらべ・しき/高大共創コーディネーター、追手門学院大学客員教授、情報経営イノベーション専門職大学客員教授。日本大学理工学部建築学科卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。私大職員、早稲田塾総合研究所主任研究員、NPO法人NEWVERY理事などを経て独立。全国の高校や進路指導協議会で進路指導に関する講師を務めている。著書に『ミスマッチをなくす進路指導』(ぎょうせい)など。
こちらの記事もおすすめ 【超速報】東大合格者「高校別」トップ20! 開成149人、聖光学院97人、灘94人…公立で上位に食い込んだ名門校は?