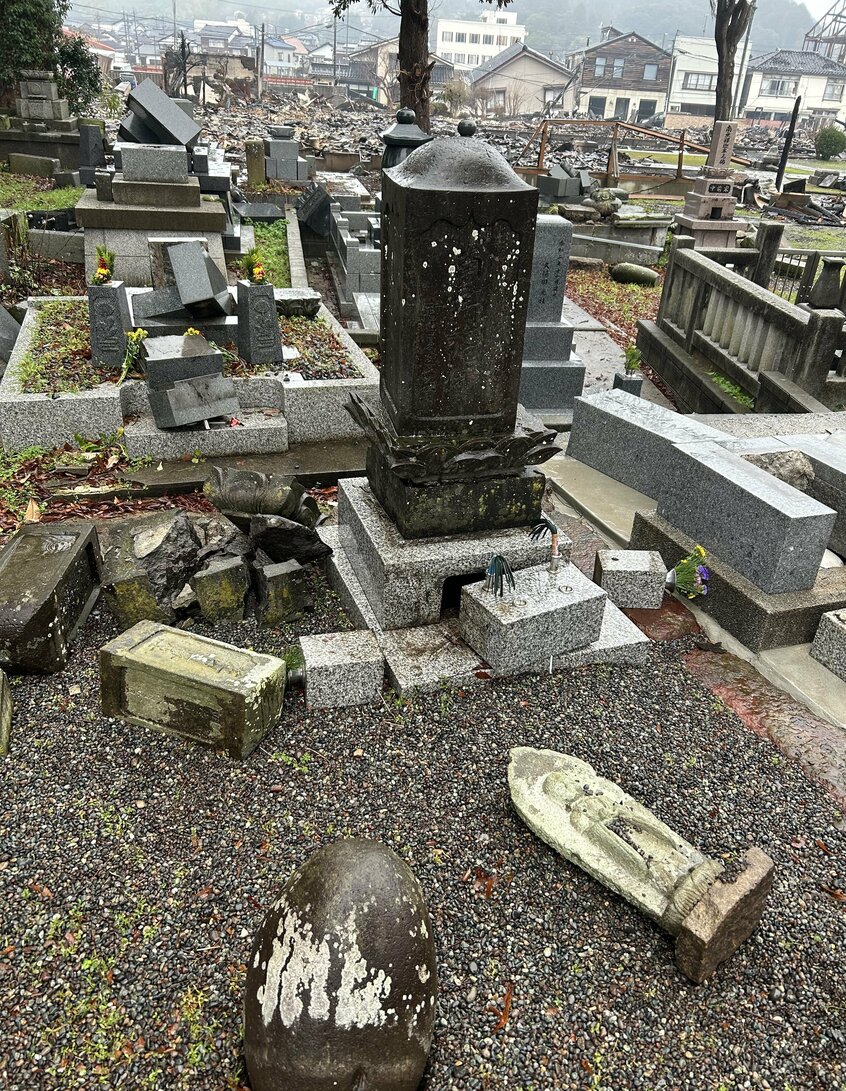
関西地方から派遣されたという彼は20歳。元日に親戚で集まり、すしを食べようとした瞬間に震災が起き、そのまま招集された。初めての災害派遣の現場では、輪島市と外部をつなぐ交通路を確保する業務にあたっているという。
午前4時起床で2時間しか眠れない日々が続き、彼女からは「生きてる?」と不安でたまらない様子のLINEが頻繁に届く。保存食の米は、「古いと消しゴムを食べているよう」だというが、「誰かを助ける仕事がしたくて自衛官になったので、つらくはないです」。
そして午後10時ごろ、同僚と合流すると、再び仕事へと戻っていった。
危険と隣り合わせの被災地で、記者も神経が高ぶっていたせいだろうか。なかなか寝つけず、こま切れの睡眠をかろうじて3時間ほどとった翌朝7時。車の外に出ると、焦げくさいにおいが混じった南風が、頬に吹きつけた。
街の様子を見に、再び朝市通りのほうへと歩く。重苦しい雲が立ち込めていた前日とは打って変わった青空は、その下の壊滅的な光景とあまりにも不釣り合いに感じた。
「もうダメです」
朝市通り周辺の焼失エリアからわずか数百メートル手前で、ヘルメットをかぶって自宅前にたたずむ男性と出会った。
「家の片付けをしとる」と話してくれたのは池高精一さん(75)。前日は、壁がはがれ落ちた1階部分に木の板を打ちつけたので、この日は散らかった室内を少しでも片付けようと、避難所からやって来たという。
池高さんは、仏壇や仏具などを手がける漆塗り職人。1階が住居、2階が工房だった自宅は、周囲の家の大半が倒壊しているのにもかかわらず、しっかり原形をとどめている。
「この家は俺が小学生のころにできたから65年くらい経ってるけど、おやじがいい材料を使ってくれたんだろうね。でも、中にあるもんは全部落ちて、2階は壁も落ちて、もうダメです」
家の中を見せてもらうと、障子やタンスが倒れ、押し入れの中のものが飛び出し、足の踏み場もなかった。2階では崩れ落ちた壁が床の上で粉々になっており、塗られる前の「経机(きょうづくえ)」と呼ばれる仏具も壊れて散乱していた。




































