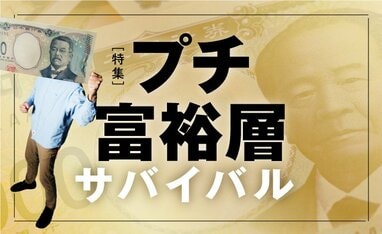子どもにはオナラがウケるだろうと思い、『ドレミのうた』の替え歌で全部の音階をオナラの音に変えた歌を披露したところ、ウケたのは最初の「ド」だけで、2つ目以降のオナラがすべてウケないという地獄を味わったこともあった。
いきなり全力でネタを始めると泣き出したりするし、一方的にネタをやるだけでは退屈してしまう。声を出させたり、ボールを投げさせたり、風船を使ったり、飽きさせないための工夫を繰り返してきた。
また、演出の中には「ためになる」という要素も入れた。子どもに早起きを勧めるヒーローや、洋菓子より和菓子の方が血糖値が上がりにくいという知識を教えてくれる「あずキング」というキャラクターを演じたこともあった。
早稲田大学卒も生かして
子どもにとってためになるという要素を入れておくと、保護者を喜ばせることができる。子どもをライブに連れて行くかどうかを判断するのは保護者の役目である。小島はそこにも配慮していた。
試行錯誤を繰り返しながら、小島は徐々に子ども向けの芸人として実績を作り、認知されるようになっていった。子ども向けのライブや営業活動は、多いときで年間100本以上にもなるという。
芸人としても地道にネタを作り続けて、2016年にはピン芸日本一を決める大会『R-1ぐらんぷり』で準優勝を果たした。
その後、新型コロナウイルスの感染が拡大すると、YouTubeで子ども向けの算数の授業動画を配信し始めた。子どもを相手にした活動を続けてきた経験と、早稲田大学出身の頭脳を生かして、わかりやすく面白い授業を行い、ここでも子どもたちの心をつかんだ。