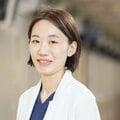「この場合は、慢性的な疲労の蓄積のほか、適応障害やうつ病、睡眠障害などの精神疾患、あるいは身体疾患など何らかの疾病の可能性もあります。産業医に相談したり専門医の診断を受けたり、最近の働き方やプライベートを含めた負荷や生活を見直すといった、自身の健康を取り戻す活動もぜひしてもらいたい」
もし職場環境や仕事内容で自分の健康に負担になっているところがあれば、上司や同僚に相談し仕事側からの改善策を考えてみることも大切だ。もちろんそんなときも産業医が役立つことが多いので相談しよう。
勤務状況は上司の声かけで変わる可能性も
休みをとりやすくするには上司の日頃からの声かけも大事。若い人材の流動性が高くなり、さらに多様性が求められ、ハラスメントに該当する事柄も明確に示されるようになった。部下にどのように関わったらいいか難しいと感じる人も多いだろう。それは、有休取得だけにかかわらず、当日欠勤についても同じことがいえる。
「部下からお休みの申告が来たときには、すでに体調や精神面での限界を超えていて、診断書を伴って翌日から休職に入ってしまうケースもあります。そうならないためにも、部下からの申告を待つばかりではなく、日頃から体調を気遣う声かけをしていきたいですね」
部下を気遣う声かけは、少し考えただけでも「最近ミスが多いけど何かあった?」「顔色が悪いけど体調は問題ないか?」「遅刻ギリギリが続いているけど疲れてない? ちゃんと眠れてる?」「有休とってリフレッシュしていいんだよ」など、いくらでも出てくる。
さらに、上司がロールモデルとなり、積極的に休暇を活用する姿勢を見せるとなおいい。疲れたら休んでいいんだ、体調不良でなくてもリフレッシュのため予防のため休暇を取得してもいいんだと見せることが効果的だ。
普段から、声かけを意識し上司自らが実践することで、働く現場に休みやすい空気感が生まれ、部下は計画的に休暇のスケジュールを立てやすくなる。さらに、体調不良による当日欠勤や労働力の大きな損失である休職防止にもつながる。