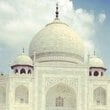老親と中高年のひきこもりの問題が、社会課題として認知されるようになった。ひきこもりといえば、男性をイメージしがちだが、実は中高年では女性の方が多い。女性がひきこもる背景には何があるのか。AERA 2023年9月25日号より。
* * *
近年、女性のひきこもりが多いことにも注目が集まっている。内閣府の2022年度「こども・若者の意識と生活に関する調査」の調査によると、ひきこもり状態にある40~64歳のうち、女性は半数以上の52.3%。15~39歳でも、女性が45.1%を占めた。「KHJ全国ひきこもり家族会連合会」共同代表の山本洋見さんは、「数字が実態に追いつき、顕在化しただけで、以前から悩む女性は多かった」とした上で、こう指摘する。
「女性は独身であれば、家事手伝いや嫁入り修業中。主婦や子育て中では自ずと社会との接点があると思われがちでしたが、家族以外とは接点をもたず、必要最低限の外出しかしない人は多くいます」
16年から全国で「ひきこもりUX女子会」を主宰してきた一般社団法人「ひきこもりUX会議」代表理事の林恭子さん(57)は、女性がひきこもる理由と背景をこう説明する。
「良き娘、良き妻、良き母であることを求められ、さらにフルタイムで働いて社会で活躍することが最先端のような風潮があります。プレッシャーが非常に大きく、それをこなせない自分を徹底的に責めてしまったり、抱えている生きづらさを夫や家族がわかってくれないと感じたりすると、より孤独感が深くなってしまう」
その言葉にうなずくのは、都内の女性(38)だ。教育熱心な両親のもと、中学受験をして私立に入学したが、集団生活になじめず、低血圧な体質もあって遅刻と欠席を繰り返した。いつも怒っていた母は、中学の終業式の日に菓子折りを持って職員室までお詫びに行ったという。そんな姿を見た女性は、
「自分の努力不足だと落ち込みました。両親からは良い大学へ進み、きちんと正社員で働いてほしいという圧を感じていたけれど、進学できたのはFラン大学。授業中にお菓子を食べながらおしゃべりしているような環境で、ここは幼稚園なの?と。周囲の誰ともうまくいかなかった」
21歳で大学を中退し、ひきこもった。その頃、父が他界し、折り合いの悪い母との生活が始まった。体調が良くなれば、工場や印刷会社で派遣社員として働いたが、職場の人間関係に疲れることが多く、続かなかった。強いストレスを感じると散財してしまい、クレジットカードと携帯電話が止まったこともある。30歳の頃に病院で発達障害の疑いがあると指摘されて、「自分が悪いわけじゃなかった」と少しラクになったという女性は、いま仕事を探している。