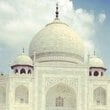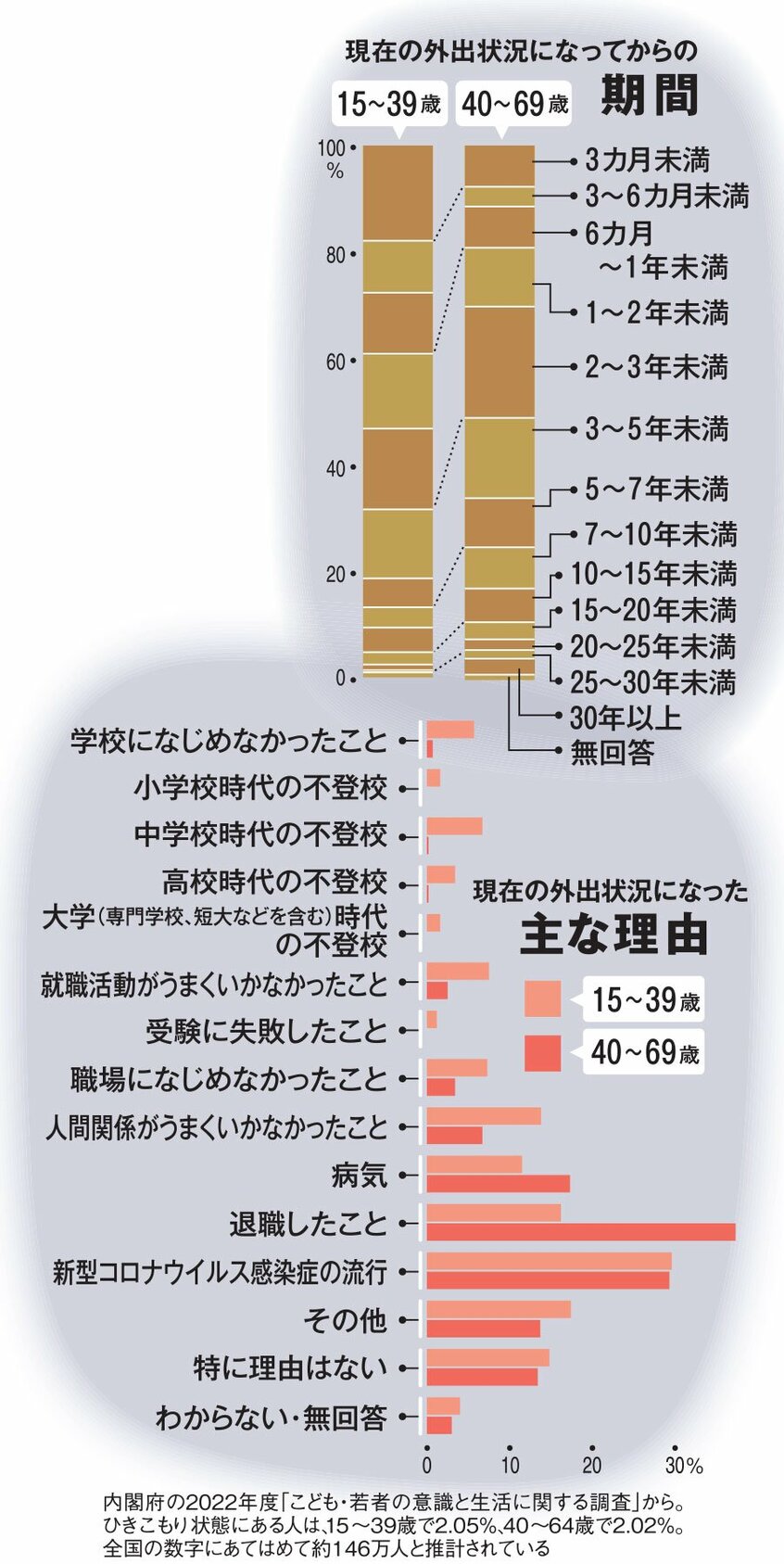
「私はFラン大卒で資格がなく、実務経験もない。就職に強いカードを何も持っていません。でも、働きたいんです。コミュニケーションが苦手だから、接客は難しいし、できれば在宅でできる仕事がいい。1人暮らしもチャンスがあればしてみたい」
ひきこもりUX女子会を主宰する林さんはこう話す。
「コロナ禍を経て、リモートワークが定着したので、自分に合った働き方を多少見つけやすくなったのではないでしょうか。『親が生きづらさの原因であり、同時に命綱』という状態を脱するためにも、1人暮らしは大切な転機。各地にある空き家や団地を活用するなどした居住支援の体制もあればと思います」
林さんは高校2年から約20年ひきこもった経験がある。
「もう一度、生きていこうと思えるまで、それだけの時間が必要でした。一方で、青春が全くなく、失ったものがあまりに大きかったので、ひきこもりを『良い経験』とか『だから今がある』とは思っていません。再び社会とつながりやすくなるよう仕組みを整えていってほしい」(林さん)
家庭だけで抱え込まないことも重要だ。約30年間、ひきこもり支援を続けている「市民の会エスポワール」代表の山田孝明さん(70)は、
「子どもが50代になると、就職が格段に難しくなり、親も無理がきかなくなる。『8050』になる前の『7040』のうちに支援団体とつながっておくべきです」
と訴える。(編集部・古田真梨子)
※AERA 2023年9月25日号より抜粋