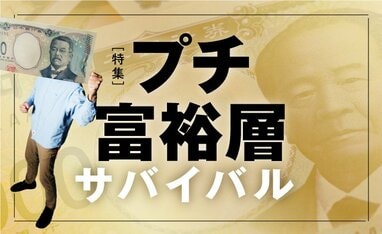田原:どういうこと?
宮田:デモの呼びかけなどでSNSが役立ったのは事実ですが、一方で、負の側面も明らかになってきました。人と人をつなぐアルゴリズムそのものの歪みです。メタやグーグルといったSNSの運営会社は、ユーザーをいかにサイトに長くとどまらせて広告を見せるかを考え、巨額の収益を生み出します。この滞在時間最大化モデルによって、人々は自分にとって心地よい情報をより多く見せられ、やがてそうした情報しか見なくなる。そうなると世界中で極端な思想がより極端になっていくということが起こり得ます。人と人がつながるはずの技術が、むしろ分断を生んでいるのです。
田原:日本では昨今、「生きづらい」という言葉がよく聞かれます。デジタル社会が発達して便利になれば生きやすくなるはずなのに、なぜなのでしょうか。
宮田:本来デジタル技術は、多様な人たちの豊かさを支えるためのものです。ただ、人同士が簡単につながれることによって、お互いが「こうあるべき」というような同調圧力を加速させてしまう側面もある。それが生きづらさとして表れるのではないでしょうか。
田原:社会の状況に目を移すと、生きづらさにつながる貧困問題も深刻です。日本は働く人の4割が非正規雇用で、女性にいたっては5割以上です。
宮田:企業にとって、バブル崩壊時のリストラがトラウマになっているのでしょう。正規職員を解雇するのは大変だが、非正規であれば……といった考えが続いている。さらに、何かが起きても解雇せずに済むよう、稼いだ利益を内部留保に回して投資をしなかった。
■失敗が怖くなり挑戦やめた日本
田原:1980年代は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われ日本経済は世界一だったのに、ものすごい凋落ぶりです。
宮田:この30年間、日本経済は成長していないと言われますが、日米で比較すると、グーグルやアップル、マイクロソフト、アマゾンといった米国のテックジャイアント(情報技術の巨大企業)5社の分を除けば日米の経済成長はほぼ同じなんです。この5社が飛び抜けている。そうした新たな企業を生み出すことができなかった日本は、デジタル技術に対する適応が十分ではなかった。