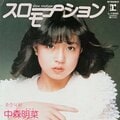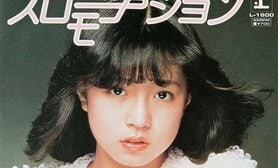田原:インターネットが日本に普及し始めたのは90年代後半。そのころは不況のどん底で企業はITに参入できなかった。不況で経営者たちの考え方も変わり、失敗を恐れるようになった。ソニー創業者の盛田昭夫さんが常に私に言っていたのは、ソニーは世界のどの市場も手をつけていないものを開発する。そうすれば付加価値がつく。これを皆がやれば経済成長すると。ただし、どの市場も手をつけていないことに挑戦すると、必ず3回、4回は失敗する。それを覚悟しなきゃいけない。バブル崩壊後の経営者は3回、4回失敗したら交代させられてしまうから、失敗が怖くなって盛田氏的な経営をやめてしまった。
宮田:ジャパン・アズ・ナンバーワン時代の成功モデルに固執して挑戦しなくなった。意欲がなくなったとも言えますね。
田原:意欲といえば、僕は65年に行ったソ連での出来事が忘れられない。ソ連は共産主義で、平等でなければいけないから競争を認めない。つまり意欲を認めないんです。競争もないのに企業はやっていけるのかと疑問に思った。トラック会社を取材すると、競争は禁止だけどノルマはあると言う。当時、ソ連のトラック会社はどこも大型しか作っていなくて、なぜ小型や中型を作らないのかと聞いたら、ノルマは年間にどれだけ鉄を使うかなんだと。ニーズなんてどうでもいいんだね。
宮田:同じようなことはAI時代にも起こり得ますね。指標の数字ばかりを見ていると、実態が歪んでいても気づかないまま走り続けてしまう恐れがある。
田原:国際情勢についても聞きたい。先ほど、分断が進んでいるという話がありましたが、米国のトランプ氏が2016年の大統領選挙で、それまでの候補者が全く言わないことを初めて宣言した。「世界はどうでもいい、米国さえよければいい」と。これを米国民は支持して、トランプ氏は当選した。それまでの米国はグローバリズムで、人、物、カネが国境を超えて活躍できたが、米国の経営者は工場を賃金の安い他国に移してしまい、自国の工業地帯が廃墟同然になって失業者が増えた。そこにトランプ氏が「世界はどうでもいい」と言って出てきた。反グローバリズムですね。