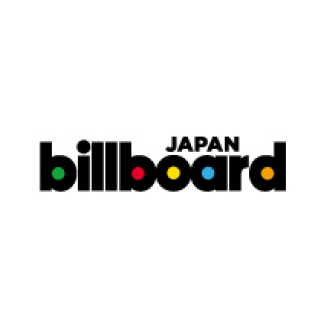「ビヨンセの妹」という半ば強引なキャッチコピーでリリースした、2002年のデビュー作『ソロ・スター』は、何というか“やらされた”感満載で、痛々しかった。2ndアルバム『ソランジュ&ザ・ハドリー・ストリート・ドリームス』(2008年)は、幅広いジャンルの音を取り入れた意欲作で、アーティストへ“脱皮”した感じはしたが、まだどこか納得いかないもどかしさがある。
転機となったのが、そこから8年後の2016年にリリースした3rdアルバム『ア・シート・アット・ア・テーブル』。純度100%のソウル・ミュージックのみで構成された本作は、その世界観が彼女のキャラクターにぴったりハマり、多くのリスナーを惹きつけた。大衆には決して媚びない、ソランジュというアーティストが誕生した大傑作だ。
そこからおよそ2年半ぶりにリリースされた本作『ホウェン・アイ・ゲット・ホーム』は、前作で確立したスタイルをそのままに、ジャズやブルース、ファンクなども取り入れた、ブラック・ミュージックの真骨頂ともいえる作品に仕上がっている。リリース後、ツイッターのトレンドで1位を獲得するなどSNSでの反響も大きく、姉・ビヨンセも、自身のインスタグラムにカバー・アートやミュージック・ビデオを投稿し絶賛した。
前作同様、インタールードを随所に挟み、“繋ぐ”ことで一曲一曲の良さを際立てている。オープニングのアナログ・メロウ「Things I Imagined」~同米ヒューストン出身のデビー・アレンとフィリシア・ラシャドをフィーチャーした「S McGregor」(インタールード)~清涼感のあるネオ・ソウル「Down With the Clique」と、冒頭3曲から期待に胸膨らむ。次曲「Way to the Show」もそうだが、“どうよ、聴きなさい”という威圧感を一切感じさせない、自然体のボーカル・ワークが聴き心地良い。
メトロ・ブーミンがプロデュースした「Stay Flo」も、彼がここ最近ヒットさせたグッチ・メインの「I Get the Bag」や、21サヴェージの「Bank Account」などのトラップ・サウンドとはまったく違う、ジャジーなトラックに仕上がっている。本作には、そういった“大衆に媚びた”タイトルは一切ない。
2000年代を代表するサウンドメーカー、ファレル・ウィリアムス&ザ・ドリームとタッグを組んだ、プレイボーイ・カルティとのデュエット曲「Almeda」は、米ヒューストンのヒップホップ・カルチャーについて歌われた曲。「アルメダ」とは、彼女の故郷でもあるヒューストン地域のひとつで、肌の色や髪型、葉っぱにお酒などのワードを盛り込み、アルメダの黒人文化をラップするように継ぎ当てていく。プレイボーイ・カルティの他には、 英ロンドン出身のシンガーソングライター=サンファと、前述のグッチ・メイン、米ブルックリンのヒップホップグループ=スタンディング・オン・ザ・コーナーがゲスト参加した。
デヴ・ハインズ(ブラッド・オレンジ)とアール・スウェットシャートによるプロデュース曲「Dreams」もすばらしい。詞・曲共にコンパクトな仕上がりではあるが、浮遊感漂うソランジュのボーカルと、生楽器によるサウンド・プロダクションが、タイトルの世界観を見事表現している。繊細で華奢なハイトーン・ヴォイスが続く「Jerrod」も好曲。間髪入れずにはじまる「Binz」は、アニマル・コレクティヴのパンダ・ベアとザ・ドリームがプロデュースした、アフリカン・テイストのミディアム。喋る感覚で言葉を紡ぐソランジュの歌業には、恐れ入る。
サンファがバックを務める、ジャズ・プロダクションに近い「Time (Is)」や、グッチ・メインとラップを絡め合うヒップホップ・トラック「My Skin My Logo」では、男性陣には決して飲まれない“女性の強さ”みたいなものを感じさせられた。アンニュイな雰囲気を醸し出す「Beltway」~雨音と鬱々しさを表現した「Sound of Rain」、菩薩のように柔らかい口調でたしなめる「I’m a Witness」と、最後まで一級品の作品が続く。
本作のテーマは「原点への探求」とのことで、故郷ヒューストンからはデビー・アレンやフィリシア・ラシャド、アフリカ系アメリカ人の詩人、故パット・パーカーもインタールードに起用されている。独立した黒人女性の美しい姿を描いた、彼女のキャリアにおける最高傑作。どうしても付いてまわるものではあるが、「ビヨンセの妹」という売り文句も、もはや必要ないだろう。
Text: 本家 一成