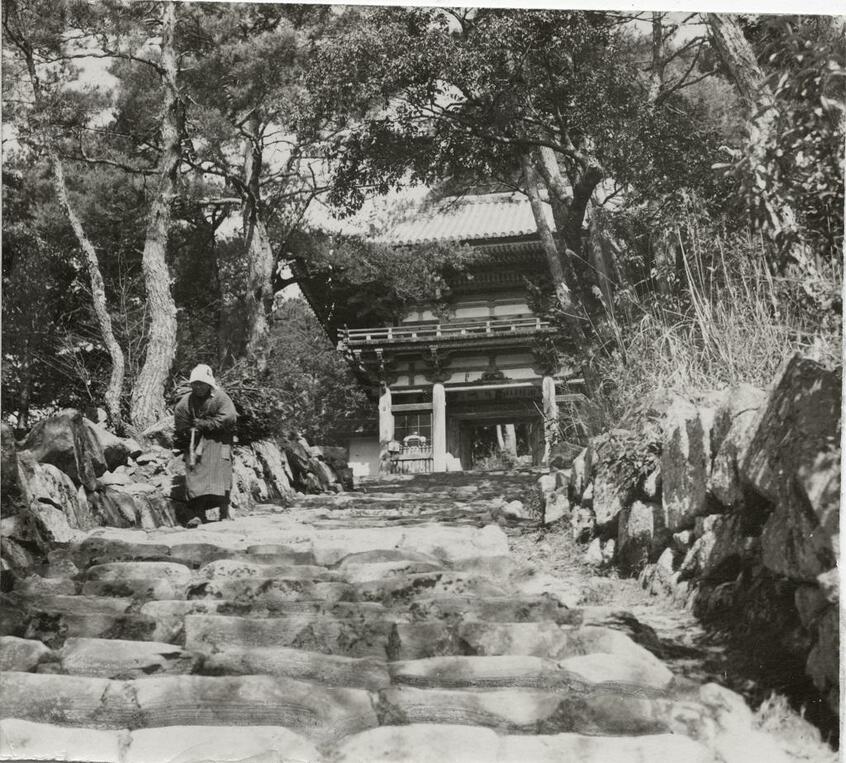
平山:信長が城下を楽市にしたのは、近江から京都に通じる大動脈を、脇の安土に道をつけて引き込まなきゃいけなかったからなのです。
千田:はい。街道を付け替えちゃいました。かなり強引な信長のやり方ですね。また城のシンボルだった天主(天守)は、信長が安土城(滋賀県)で始めたと伝えられていましたが、最近の研究では安土城の前に、畿内では天主と呼ぶ特別な建物を城に建て始めていたとわかりました。だから天主は信長の発明というよりは、畿内に成立していた城の中心建物を信長が再定義して、より巨大化してできたと再評価できます。
平山:武田家の江尻城にも高楼がありました。それが武田の天主と言われるものだと思われます。城主は守りのために遠くを見つつ、権威を誇示するのでしょうね。
千田:シンボルとしては圧倒的ですね。
平山:当時は五重塔などの寺院建築以外に高い建物はないので、大名が高い建物で財力と権力を誇示する意味は大きいです。
■美を強く求めた信長の安土城
千田:城のつくりで言うと、安土城の瓦はオリジナルデザインで整えて金箔(きんぱく)を施していた。見えない細部まで美を尽くしたのは、信長の人柄が出ていると思います。一方、秀吉は安土城よりも大きな天守をつくったけど、大坂城の瓦のデザインはバラバラです。
平山:信長はこだわりがあったのでしょうね。安土城の瓦を焼いたのは、「唐人一観」と『信長公記』に出てくる中国から来たデザイナーなんですよ。
千田:安土城の発掘成果では、瓦は大和(現在の奈良県)の技術でつくったのが判明しているので、通常の瓦の製作に唐人一観が関わったのではなく、私は天主をはじめとした大棟の上にそびえた鯱の創造に関わったデザイナーが一観だったと考えています。そして、これまで家康には「ケチ」疑惑があって、信長や秀吉のような豪華絢爛(けんらん)な城はつくらなかったと言われてきましたが、近年の調査によると、家康も信長や秀吉に負けないすごい城をつくったと考えられます。





































