
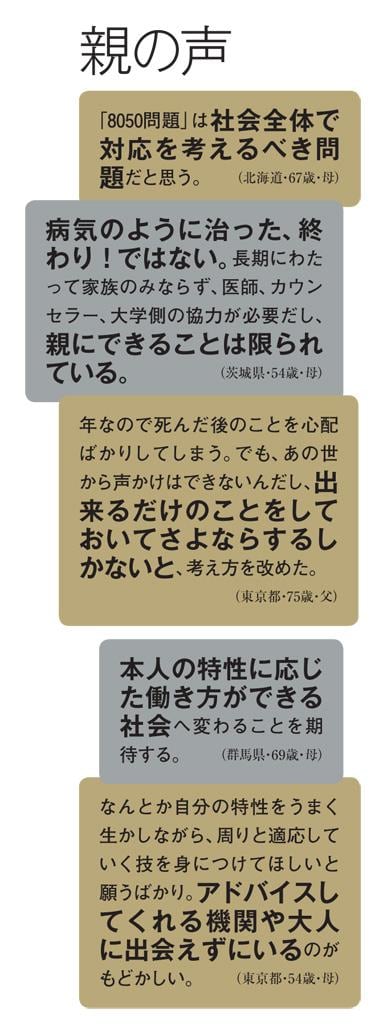

中高年のひきこもり状態にある人の推計は61万3千人。若年層も合わせると、総数は100万人超とみられる。中高年の子と高齢の親が社会から孤立する「8050」問題は、特殊なケースではなくなった。当事者たちは何に苦しみ、何を思うのか。ノンフィクションライター・古川雅子氏がリポートする。
* * *
山形県米沢市の市営住宅に暮らす母親(86)は、ひきこもって16年になる息子(42)と暮らしている。79歳まで自分がバイトに出て倹約してきたことも、努めて明るく話す。
「今日の服は私が50代の時のもの。花柄で若い人の趣味みたいで、悪くないでしょ? 痩せてブカブカなのはみっともないから、詰めて縫い直して」
息子がひきこもっていることを人前では言わずにきた。
「周りに言っても、いいことは何もなかった。私が笑顔でいて、何とかしなくちゃと。息子のダメージになるような言葉は言わないと決めていました」(母親)
地元のハローワークに足を運んでは求人情報の用紙を持ち帰り、テーブルの上にそっと置いた。折をみて家計の現状を伝えた。「お金は空から降ってこないのよ」と、通帳の残高を見せたこともある。不機嫌になりがちな息子を刺激しないよう、言葉遣いには細心の注意を払う。
父親は7年前に他界。母親自身の年金と残りわずかな貯金が、二人にとっての命綱だ。
息子がひきこもったきっかけは、仕事での挫折だった。高校卒業後に県外で自衛隊の仕事に就いたが、心身ともにハードな職務で、一番親しい同僚が自殺したのを機に「辞めたい」と訴えるようになった。4年で退職して帰郷。2年間の静養後、地元の会社に再就職したが、作業着にアスベストが付着する職場環境や社長が乱暴な言葉を使うすさんだ毎日に嫌気がさし、辞めた。当時26歳だった。
「今で言う発達障害だった」という父親に似て、息子は人との関係がうまく結べない。なんとか精神科を受診させても、言葉足らず。医師が母に家での生活を事細かに聞いたことでへそを曲げ、二度と受診しなくなった。結局、はっきりした診断はつかなかった。
公的な窓口や診療所など、「ざっと20件は相談してきた」が、具体的な支援に結びつかず、孤軍奮闘を続けてきた。
生活費をどんなに切り詰めても、1カ月15万円の年金で、家賃や光熱費、息子の社会保険までを賄いきれない。定期預金100万円が「最後の砦」だが、それも尽きかけている。口座の残高は昨年からマイナスに転じ、間もなく定期預金からの借り入れ限度額に達する。




































