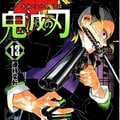13人の文庫編集長がライバル出版社のイチ押し作品を選ぶ――。そんな前例のない企画が、朝日文庫40周年を記念して全国の書店で開催中だ。角川文庫、光文社文庫、ハヤカワ文庫、朝日文庫の編集長ら4人が集まり、文庫市場や今後について語り合った。
* * *
──各社では文庫の市場でどんな戦略を考えていますか?
小口(光文社文庫):光文社文庫はミステリーと時代ものが多いので、より若い人にアピールするために、個性的なキャラクターが活躍するキャラクターノベルを増やして、読者層を広げていこうとしています。今年、「光文社キャラ文庫」を創刊しました。編集と営業が、より密に話し合って戦略を練っていく必要も感じています。
塩澤(ハヤカワ文庫):ハヤカワ文庫はSFとミステリーが中心ですが、翻訳ものが以前ほど動かなくなってきたこともあって、ここ2、3年、書店さんにご協力いただいて、国内ものを売る取り組みを始めています。昨年、早瀬耕さんの『未必のマクベス』を文庫にする際に、単行本のときに高く評価してくださったエキナカの書店さんに単店で仕掛けてもらって、千冊くらい売っていただきました。それを他の書店さんに少しずつ広げていって、今9万部になっています。
長田(朝日文庫):私はハヤカワ文庫からはウイリアム・アイリッシュ『幻の女』を選びました。久しぶりに読み返して、最後のどんでん返しに驚愕しました。
塩澤:『幻の女』もそうですけど、翻訳ものが厳しくなってきたとはいえ、アガサ・クリスティーなど評価の定まっている古典はやはり強いんです。ジョージ・オーウェル『一九八四年』は、2009年に別の翻訳で文庫に入れ直しましたが、トランプ大統領になってから話題になり、累計で27万部売れています。
──それはすごいですね。
塩澤:昨年10月にカズオ・イシグロのノーベル賞受賞が決定してから、ハヤカワ文庫が独占的に出している文庫が8点で125万部も重版しました。副社長が結婚するとき、イシグロ夫妻が仲人をしたくらい、オーナーの早川家との関係が深い。老舗翻訳出版社の強さを感じます。