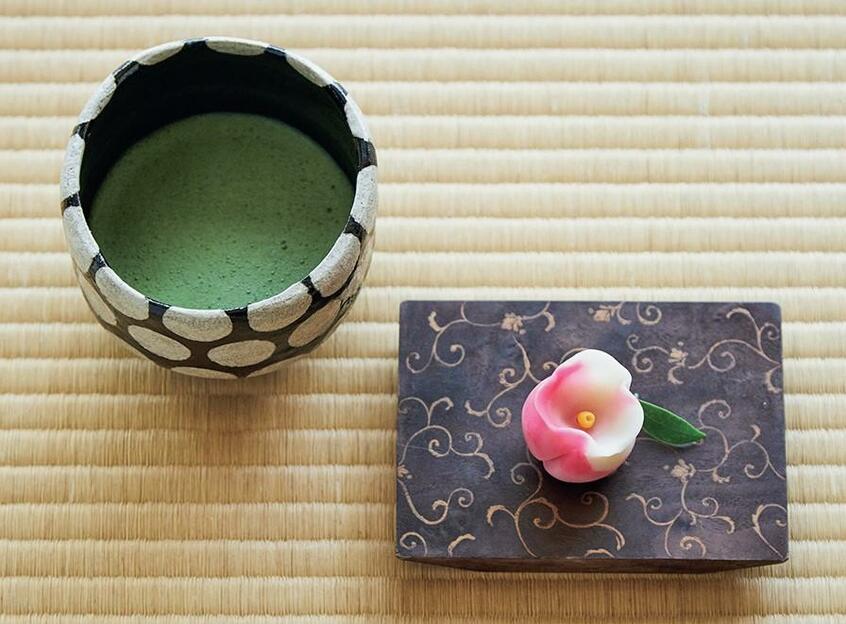
利休が秀吉によって切腹に追いこまれたのち、養子の少庵が京千家の長になり、利休のお茶を守ります。少庵と利休の娘・お亀との間に生まれた宗旦がさらにそのあとを継ぎ、四畳半の茶室・又隠(ゆういん)や一畳台目の今日庵などをつくります。そして、宗旦の三男であった宗左、次男の宗守、四男の宗室が独立したことで三千家がはじまります。宗左の茶室・不審庵は通りの表に面していたことから「表千家」、宗室の今日庵は裏に面していたことから「裏千家」、宗守の官休庵は武者小路通にあったため「武者小路千家」とよばれました。
三千家はそれぞれ大名のおかかえとなり、茶道界の三代ブランドとして名声を確立。明治維新では、茶道をはじめとした伝統文化は文明開化の影響を受けたものの、財閥の支援や女学校への導入などによって、茶道は再評価されていきます。昭和に入ると、ラジオや雑誌などのメディアを通じて、茶道文化は社会により広く浸透していきます。茶道人口の大部分を女性が占めるようになり、「華やかなお稽古ごと」というイメージが定着していきました。
(構成 生活・文化編集部 端 香里/写真 松永直子)
【出版記念イベントを開催します】
松村宗亮さんの初著書『人生を豊かにする あたらしい茶道』発売を記念して、代官山 蔦屋書店にてトークショー&お茶会を開催します。
4月20日(木)19:00から
https://store.tsite.jp/daikanyama/event/humanities/32559-1941080321.html
こちらの記事もおすすめ 「烏帽子は絶対NG!」わがままで足利将軍の元服儀式を中止させた大ヒンシュクな武将は? 織田信長に与えた多大な影響(オカルト武将)





































