
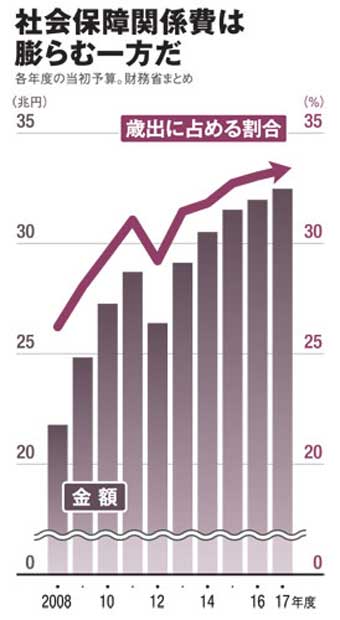
世界経済は心地よい「適温」にある。痛み伴う改革は後回しになりがちだ。しかし、いまこそ中長期の戦略を――経済同友会の小林喜光・代表幹事が語る。
* * *
未来に負荷をかけない。教育を含めて将来に投資して、次の世代が日本で意味ある人生を送れるようにするのが政治の大きな役目でしょう。
足元をみると、英国のEU(欧州連合)離脱や米トランプ政権の動きなど、グローバル化や民主主義を志向した歴史が一部逆回転し始めました。背景には技術の進化もあります。生活が快適になる半面、巨大な富を手にするのは一部の投資家や経営者などに限られる。技術の発展は格差の拡大も意味します。
時代は「革命」に向けて音を立てて流れています。日本は国家として、どんな「国のかたち」をめざすのか。政治が中長期の戦略を定める必要があります。
ひとつの節目は2045年。戦後100年であり、シンギュラリティー(技術の特異点)を迎えるともいわれます。人工知能が人間の知性を凌駕して、人間の意義も問われる時期です。
――経済同友会は経営者などが個人の資格で参加する団体だ。そのトップ、小林喜光代表幹事(三菱ケミカルホールディングス会長)は安倍晋三内閣に「若者が将来に希望を持てる社会への道筋を示していくことを期待する」と求めるなど、「財界のご意見番」として知られる。
「国のかたち」は企業や人間と同じく、「心技体」で成り立っています。この三つにバランスよく目を配るのが経営です。
「体」は儲けること。企業なら本業の稼ぎである営業利益、国家ならGDP(国内総生産)です。ただ、かつて1千万円もするスーパーコンピューターを使った計算が、いまや6万円のスマートフォンの機能で実現できる。価格は下がっても効用はむしろ増し、お金をあまりかけずに人間の幸せや快適性が高められた。GDPは上げにくい。
儲けるのが「技」、文字通り技術です。環境・エネルギーや健康といった付加価値が高い分野をねらう。「体」は1カ月や四半期(3カ月)で管理。培った体力で最低10年かかる「技」の開発に取り組む。ここは安倍政権で議論が進みました。



































