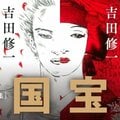もっとも、つねに中立的な立場を取るわけではない。日銀審議委員だった00年8月、当時の速水優総裁は「ゼロ金利政策」の解除を強行し、その判断が早すぎたことでデフレが長期化したと批判された。解除について協議した会合で、植田新総裁は反対票を投じている。
このケースに限らず、金融政策の転換に関する判断は非常に難しい。特に眼前では、世界的にインフレが進んで主要国が金融引き締めを続けている中で、例外的に日銀は物価上昇を誘う金融緩和を続けるパラドックスに陥っている。前出の加藤氏は苦言を呈す。
「政策の見直しは不要と言い続けながら、黒田総裁は昨年末に長期金利(10年もの国債利回り)の変動許容幅を±0.25%程度から±0.5%程度に拡大しました。しかも、理由に関する説明が曖昧で、実質利上げと市場は理解しました。こうした金融政策のランダムウォーク(方向感の定まらないよたよた歩き)は危うい」
長期金利を一定の変動にとどめるために日銀が国債を購入するイールドカーブ・コントロール(YCC)という政策には限界が生じていると加藤氏。日銀の国債保有残高は膨大な規模に達している。
■長期金利は上昇へ
「本来、長期金利は中央銀行が固定させるものではなく、債券市場での取引を通じて自然に決まるもの。国債購入の継続を表明して市場の動揺を抑えつつ、4~6月にかけて徐々に規模を縮小させてソフトランディングを図るのではないでしょうか」
植田新総裁がYCCの軌道修正に踏み切れば、長期金利が0.5%を突破する可能性も高まっていく。そうなると長期金利に連動する固定型住宅ローンの金利にも上昇圧力がかかる。
一方で、短期の政策金利予想を反映して推移しやすい2年もの国債利回りは低下気味。その状況は、植田新総裁が「マイナス金利政策」の解除には慎重な姿勢を示すと債券市場が予測している証左だろう。前出の永濱氏もこう読む。
「これまでの言動から察する限り、変動型の住宅ローン金利や中小企業の短期資金調達金利に影響を及ぼす利上げ(マイナス金利政策の解除)には慎重な姿勢を示す可能性が高いでしょう」
(金融ジャーナリスト・大西洋平)
※AERA 2023年2月27日号