
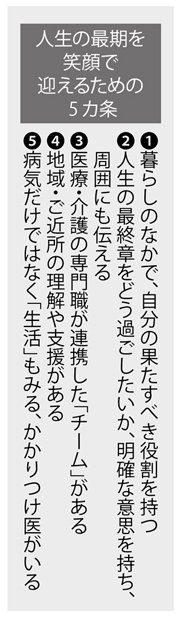
日本人の8割は医療機関で亡くなる。ところが、滋賀県東近江市の永源寺地域では、半数近くの人が自宅で最期を迎える。医療・介護・地域がつながり、「チーム」で患者を支えているからだ。チームの中心として活躍している医師に、現場の様子を聞いた。
永源寺地域は、鈴鹿山脈のふもとの山間部にあり、のどかな田畑が広がる。秋には紅葉目当ての観光客でにぎわうものの、高齢化、過疎化が進む。住民約5300人のうち、65歳以上が約35%を占める。一見すると、日本のどこにでもありそうな凡庸な中山間地域だ。そんな田舎町で“奇跡”は起きた。
入院施設はない。同市永源寺診療所が在宅医療を担っている。スタッフは、医師で所長の花戸貴司さん(47)と看護師数人。午前は外来、午後は花戸さんが車を運転し、患者宅を回る。
在宅患者は約80人。訪問診療は年1500回にのぼる。昨年は地域で亡くなった人の4割にあたる30人を在宅で看取った。
誰しも「住み慣れた家や地域で最期を迎えたい」と願う。だが、厚生労働省の全国統計によると、約8割の人が医療機関で亡くなっている。自宅で亡くなる人が「4割」というのは、驚異的な数字だ。
花戸さんが永源寺診療所に赴任したのは2000年。ちょうど介護保険制度が始まった年だった。
当時29歳。出身医大が卒業生に課す「へき地勤務の義務」に従い、ここで4年間だけ働いて再び大きな病院へ戻るつもりだった。ところが、診療所での仕事に大きなやりがいを感じるようになり、着任して18年となる今も、別の場所へ移るつもりはないという。
「最先端の医療を施し、1分1秒でも命を延ばす。それが医師の使命と疑いませんでした。でも、ここで診療を始めてみて、『それだけが地域の人たちの望みではない』と悟ったんです」
初めて在宅で看取った患者は、難病で10年近く闘病生活を送っていた。寝たきりで次第に食事ができなくなり、点滴も入らなくなった。それでもなんとかしたいと、点滴の準備を進めていたところ、背後から家族に「先生、もうあかんな」と言われた。
そのときは一瞬、反感も覚えた。
「治すために一生懸命やっているのに何を言っているのか、と。でも、生活を共にしてきた家族はもう死を受け入れていたんです。わかっていないのは私だけだった。病気だけを診ていては在宅医療はできない。その人らしい生活がどんなものか、知っていないと元気になんてできない、と教えていただいた」
多くの患者が在宅医療を望む。だが、それぞれの希望を聞いていたら、診療の手が回らない。花戸さんは自問自答を繰り返し、当然すぎる答えにたどり着いた。




































