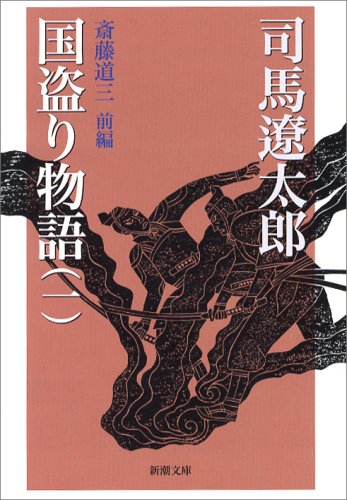
Amazonで購入する
司馬遼太郎さんをしのぶ「第20回菜の花忌シンポジウム」が2月20日に日比谷公会堂で行われ、1800人がかけつけた。テーマは「司馬作品を語りあおう──今の時代を見すえて」。作家・辻原登氏、片山杜秀・慶應大学教授、磯田道史・静岡文化芸術大学教授のほか、俳優の東出昌大氏ら4人のパネリストが活発な意見を展開した。司会は文化外国語専門学校校長で元NHKアナウンサーの古屋和雄氏。
* * *
古屋:『国盗り物語』の連載が始まるときに、司馬さんは「(斎藤)道三は過去の秩序を勇気をもって、しかも平然としてやぶった『悪人』であり、悪人であるが故に近世を創造する最初の人になった。そのみごとな悪と、創造性に富んだ悪はもはや美であることを、私はこの作品によって読者に伝えたいと思っている」と書かれています。
東出:血の匂いも感じますし、現代だったらとても凶暴な印象も受けるのですが、血湧き肉おどるというか。それを感じました。司馬作品を10代後半から読みはじめて、生き方の指針というか、男として、人としてこうあるべきという、自分の背骨を構築されたと思います。人が一生生きるにあたってどこを曲げちゃいけないのか。河井継之助、坂本龍馬、西郷隆盛もそうですけど、日本人のきれいだった気持ち、武士道だったりを学ばせていただいた。閉塞感だったり、いやな思いをしたときに司馬先生の本を読んで、こういう人間になりたいと思ったりします。
磯田:司馬文学はなぜそんなに影響力が大きいのか。『坂の上の雲』の冒頭を読んだときに気づきました。NHKで『坂の上の雲』をドラマ化したときに、今は東出さんの岳父にあたる渡辺謙さんがナレーションでいい声で読むんですよ。「まことに小さな国が、開化期をむかえようとしている」。日本列島のなかの一つの島が四国であり、「伊予の首邑(しゅゆう)は松山」という。どこからの視点か。人工衛星に乗ってるとしか思えない。司馬遼太郎さんはなにかを書かれるときに、自分を離れて天に則ったような気持ちで私をなくして、ひたすら眺める。「則天」は夏目漱石がよくいったことばです。神か天の人になったように客観的に見る視点と地を這う虫の目の二つの目玉をもっていたことが大きいと思う。
辻原:小説を書くときは俯瞰という一種の神の視点。人間を描くときは下に降りてきて、登場人物の頭の中に入る。作家はこの作業を繰り返します。司馬遼太郎の小説では非常にわかりやすく出てきます。途中で作者の意見が入ったりします。ヨーロッパでも日本でも、昔の物語はそういう形が多い。リアリティーを作者が保証するのでしょうか。歴史はすでに終わっている。どこからその終わった過去を見るか。我々は現在という場所にいて、ある程度さばいたりできる。司馬遼太郎は小説というかたちでやる。小説はつくりごとですが、読み手には本当だと思ってほしいわけです。




































