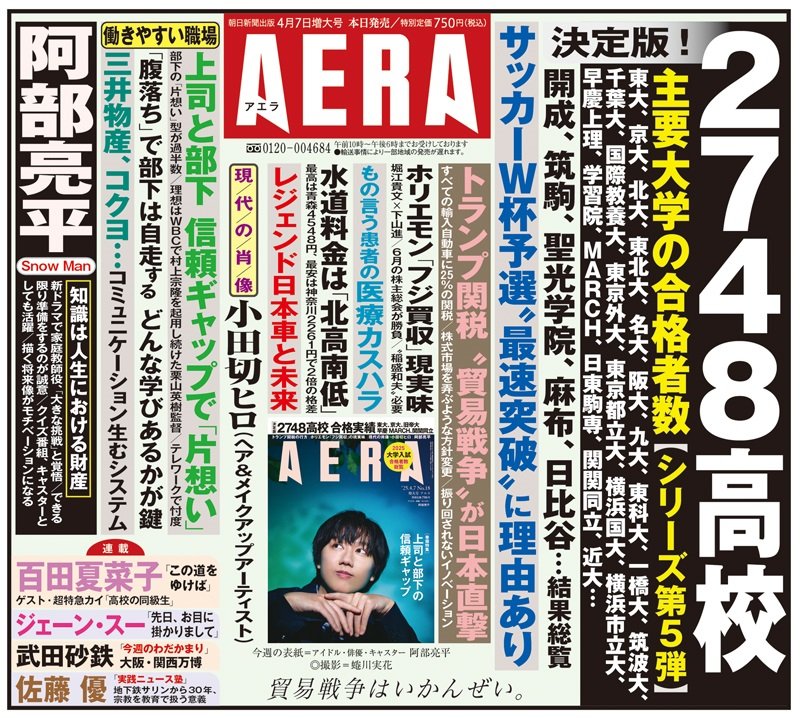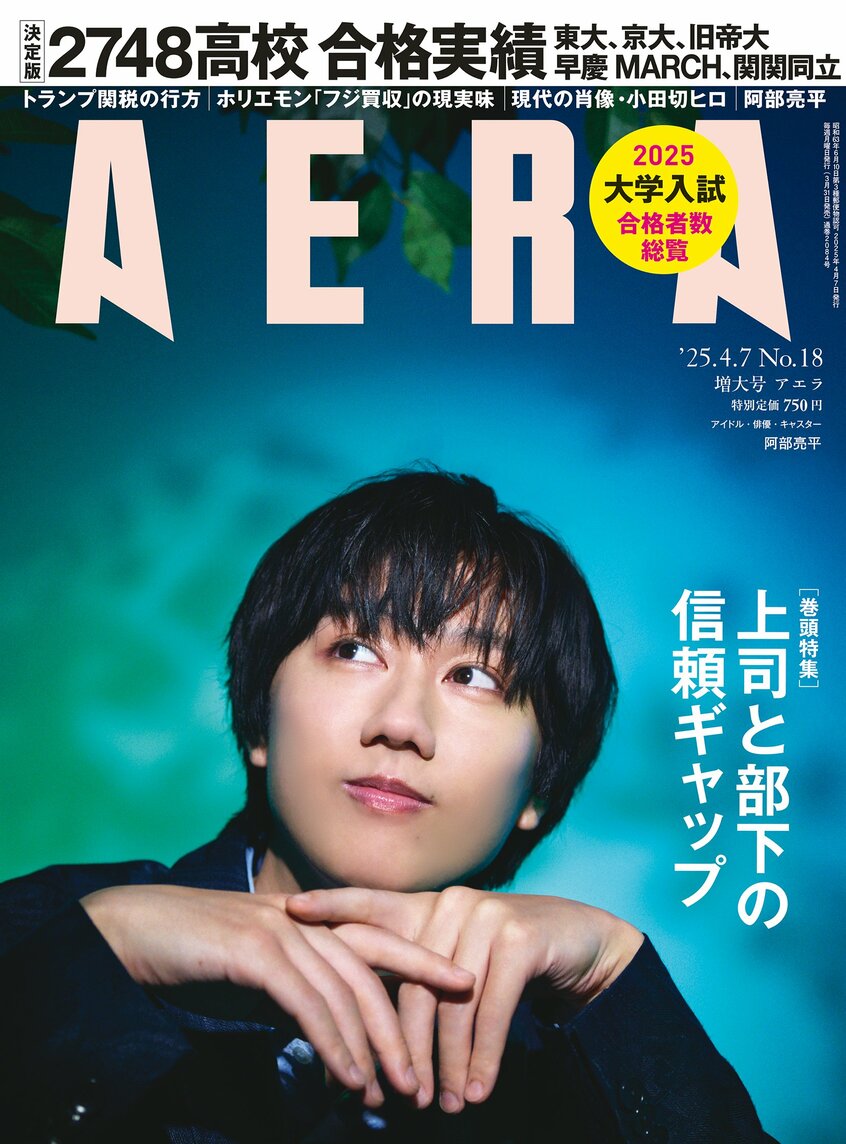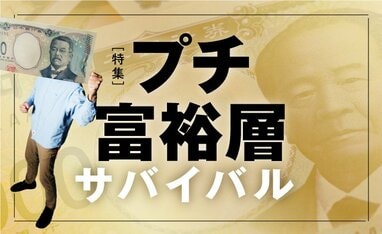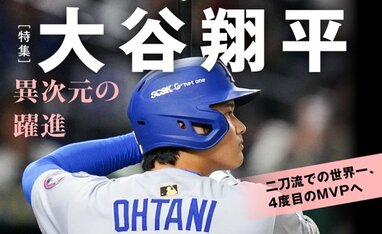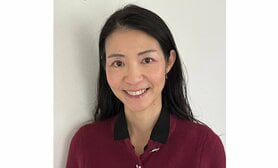富士登頂を目指す登山シーズンは、そろそろ終わりに近づいている。開山期間は山梨県側の吉田ルートが9月14日まで、静岡県側の須走・御殿場・富士宮の各ルートが9月10日まで。
だが、そんな富士山について「見る山であって、登る山ではない」と言われているのをご存じだろうか。
たいていはバスや車で五合目まで行き、そこから歩いて登頂を目指す。しかし道は砂利と岩ばかりで、登山客が行列をなし、御来光直前の山頂ともなれば、身動きできないほどの混雑も。「日本一高い山に登った」という達成感は得られるものの、「一度登れば十分」という声が少なくない。
そんな傾向に異を唱えているのは、『頂上を目指さない富士山さんぽ』の著者で登山ガイドの鈴木渉さん(37)だ。それだけで富士山に満足してしまうのは実にもったいないことだと嘆く。
「五合目から頂上までは完全に観光地化され、山歩き本来の楽しみは味わいにくい。富士山のスケールの大きさや変化に富んだ真の魅力を味わうなら、ぜひ山腹を歩いてほしい。これからの季節は紅葉が楽しめます」
五合目より下ならば春から秋にかけて、場所によっては一年中、山歩きを楽しむことができるというのだ。そこで8月下旬、鈴木さんが秋に引率するツアーの下見に同行した。
記者が歩いたのは、「御庭山荘」というかつての山小屋から「大沢崩れ」という崩壊地を目指すコース。標高2200~2400メートル付近を歩くのでアップダウンがほとんどなく、「五合目からの登頂の3割程度の体力レベルで大丈夫」と鈴木さんが言った。
当日朝、マイカー規制のために富士北麓駐車場で車を降り、バスに乗り換える。平日なのに午前9時半発の便はすでに満席で、10時発に。30分ほどで「御庭」のバス停に着いた。降りたのはわれわれだけ。
トイレをすませて10時40分、「御中道(おちゅうどう)」と呼ばれる道を歩き始めた。富士山五合目あたりを鉢巻き状にぐるっとまわる道で、かつては富士山登頂を3回成し遂げた人だけが歩くのを許されたルートだという。
石畳の上を10分ほど歩くと御庭山荘に到着した。周辺には溶岩石の斜面が広がり、落葉針葉樹のカラマツが生えているが、よく見ると枝が片側に偏っていた。
「厳しい自然環境に適応するため、ダメージの少ない風下側に枝を伸ばす『旗型(きけい)樹形』です。カラマツは本来20~30メートルの高さになりますが、激しい風雪に耐えるために、ここでは2、3メートル程度にしかなりません」(鈴木さん)
うねうねと伸びる枝は盆栽のような趣だ。足元に目をやると、高山植物のコケモモが可愛らしい実をつけていた。
さらにしばらく進むと森の中へ入り、景色は一変した。木々の隙間からかすかに日の光が差し込む。地面はフカフカの絨毯のように柔らかく、コケやキノコが生えている。湿った空気にほのかに甘くかおるのはシラビソ(マツ科モミ属の常緑針葉樹)らしい。野鳥がさえずり、さまざまな草木や花が共存する森は、まるで亜熱帯のよう。都内近郊の植林されたスギだらけの低い山では出会えない光景だ。
さらに歩くと「滑沢(なめさわ)」という広大な砂利の斜面に出た。横切るように進むうち、山頂と麓を覆っていた霧が風に流され、富士山頂の剣ケ峰が顔をのぞかせた。寝転がって見上げると、視界いっぱいに空が広がった。
「空中散歩している気分に浸れるでしょ」
そんな鈴木さんの言葉に思わず納得する。
※ 週刊朝日 2014年9月19日号より抜粋