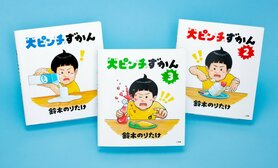日々の生活のなかでちょっと気になる出来事やニュースを、2人の女性医師が医療や健康の面から解説するコラム「ちょっとだけ医見手帖」。今回は「オンライン診療と緊急避妊薬」について、NPO法人医療ガバナンス研究所の内科医・山本佳奈医師が「医見」します。
* * *
先月23日、緊急避妊薬を対面ではなく、パソコンやスマートフォンを使用したオンライン診療によって処方してもらうことについての検討が、厚生労働省で始まりました。
厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」によると、オンライン診療とは「遠隔医療(情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為)のうち、医師―患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果を伝達する等の診療行為を、リアルタイムで行う行為」のこと。病院に行かずとも、画面を通して医師の診察が受けられるというものです。
医師法第20条では、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、 又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない」。つまり、医師による「無診療治療」は禁じられています。
ですが、厚生労働省は、情報通信機器を用いた診療は医師不足の地域に対する対処や働き方改革への対応に有用であるとのの立場で、オンライン診療を推進。昨年4月には、オンライン診療の保険適応が開始されたのでした。
■オンライン診療が普及しないワケ
当初、パソコンやスマートフォンを用いた診療の普及がより一層進むだろうと考えられていたようです。しかしながら、さほど普及していないのが現状です。なぜなのでしょうか。
一つ目の要因として、生活習慣病や難病など一部の疾患に限定されていることが挙げられます。花粉症やアトピーなどのアレルギー疾患や高血圧など、病状が安定している場合、
画面を通してのオンライン診療を活用すれば便利だと思われる病気が、保険適応から外れてしまっているのです。