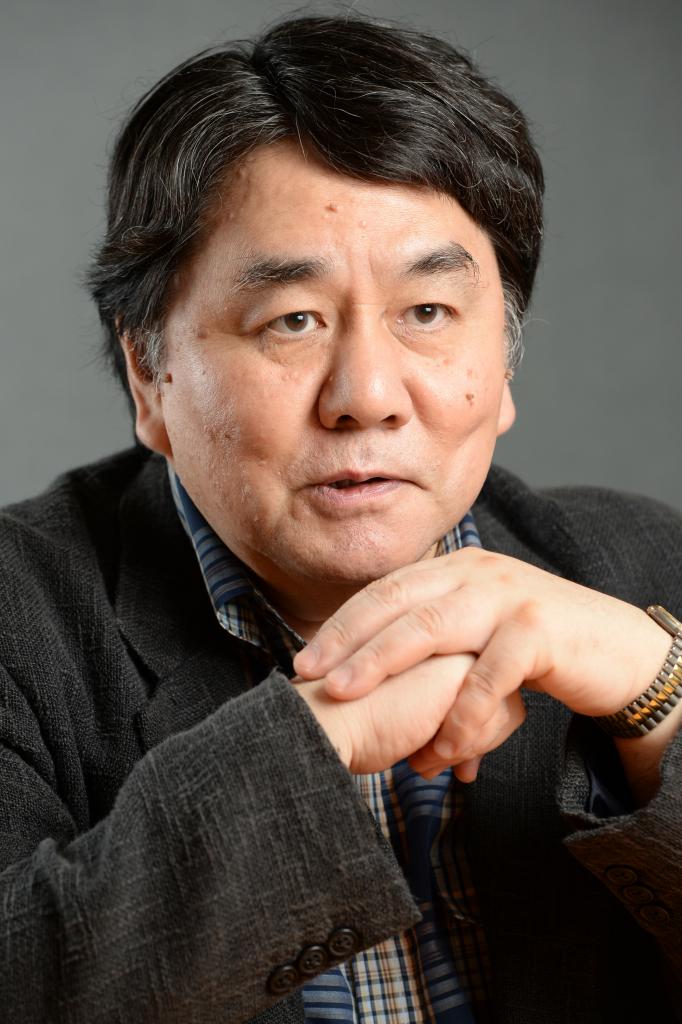
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によって1年延期された東京五輪が幕を閉じた。人の交流を避けることが求められた緊急事態宣言の中、多くの反対を押し切って開かれた大会は、五輪のあり方を問う機会となった。作家の赤川次郎さんの視点を紹介する。
* * *
「傷だらけの祭典」
<東京オリンピック2020>(実際は2021年だが)をひと言で言えば、これが適当な言葉だろう。
もともとが原発事故の「アンダーコントロール」と、「東京の七月は温暖でスポーツに最適」という二つの嘘からスタートした祭典である。平穏無事に開催できるはずがない。
それにしても安倍首相(当時)のあの発言に唖然としなかった日本人がいただろうか? 原発事故は全く先が見通せない状態だった。
さらに七月の猛暑を、どうやって「温暖な気候」に変えるのか?
だが、毎年猛暑はくり返し、さらに新型コロナという厄災が追い打ちをかける。その時点で、当然「オリンピックどころではない」という議論がわき起る、と私は思っていた。
しかし、世界でどれだけの死者が出ようと、オリンピックの準備は、何ごともなかったように進んで行った。そこにはもう想像力や良識のかけらもなかった。
そしてオリンピックは終った。
終った? 終ったのか? 本当に?
オリンピック閉会後に激増するコロナ感染者数。今、オリンピックのつけを払わされているのは、すでに崩壊しつつある医療現場で必死に戦っている医師、看護師や、そして感染しても入院さえできずに苦しむ人々である。
いくら菅首相や小池都知事が「オリンピックと感染拡大は関係ない」と言い張っても、誰が信じるだろうか。しかもオリンピック開催にあれほど執着していたこの二人が、コロナ対策となると、まるで他人事のように「人流」のせい、と言って澄ましている。
反対の声を無視して、オリンピックを強行した人々にこそ、つけを払ってもらわなくてはならない。その責任を取らせたとき、初めてオリンピックは終るのだ。




































